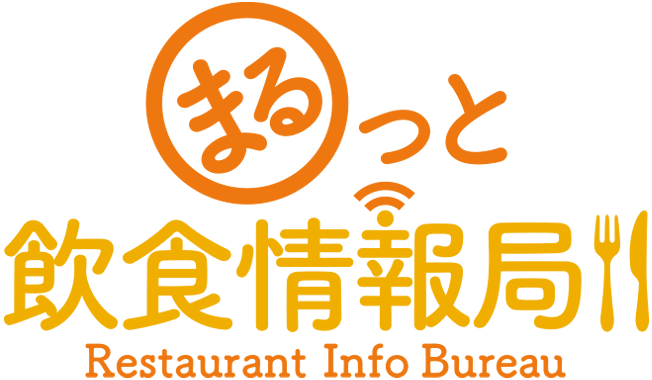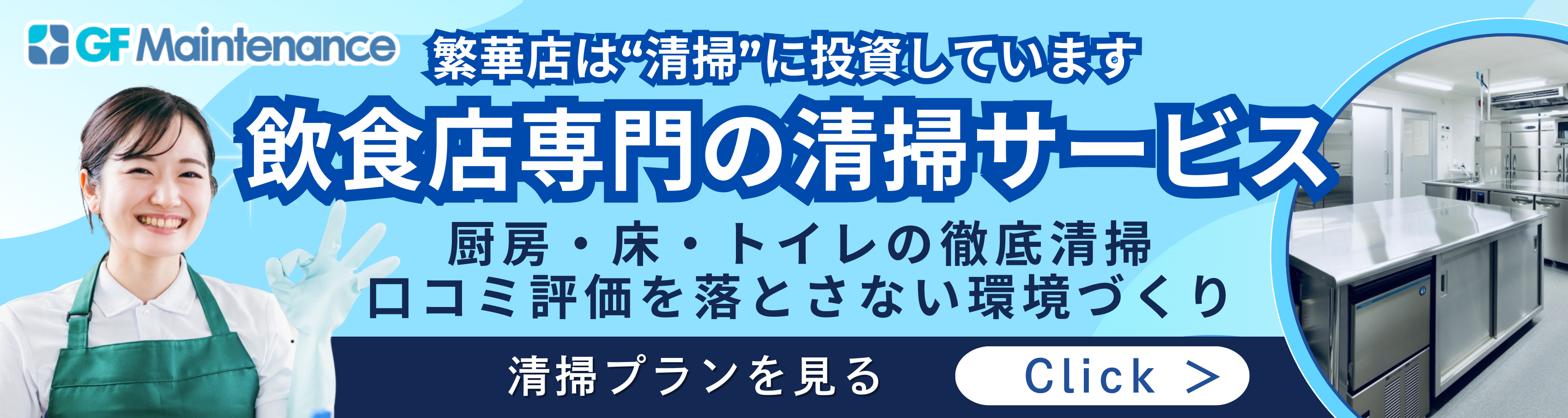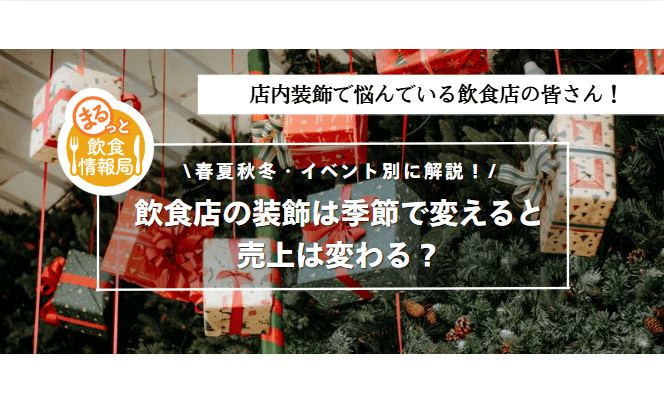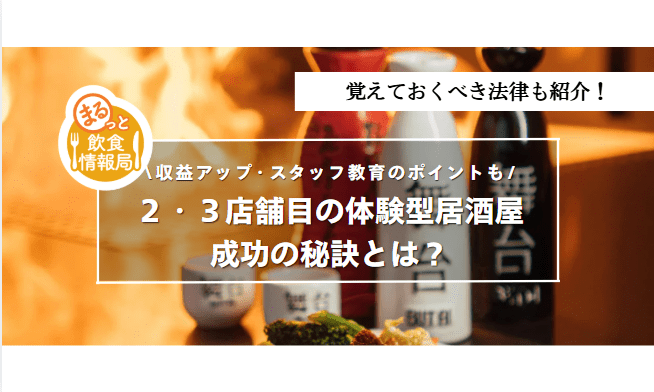2021/01/27
「ゴーストレストランは必須条件になる」と想定する食の革新者 吉見悠起氏にインタビュー

これまでゴーストレストランの事例について幾つか紹介してきたが、今回もその一つ、株式会社ゴーストレストラン研究所(本社/東京都港区、代表/吉見悠起)である。同社は東京・西麻布の住宅街の中に拠点である「Ghost Kitchens」を構え、現状16のブランドを擁してデリバリー需要に対応している。ブランドの名前は、「すーぷのあるせいかつ」「さらだのあるせいかつ」「きょうだけゆるして」「ふるーつ宅急便」「二日酔い食堂」と独創的だ。中身を見ていくと、これらは業種ではなく消費者のライフスタイルに訴求している。
このような営業形態にしている理由について、同社代表の吉見氏はこう語る。
「これまでの食産業とは、この場所で何をつくるかとなったとき、イタリアンとか和食といったことを考えてきました。これは店側の都合ですね。そうではなく、最初イタリアンでスタートしても、地域の人がそれを求めていなければ変わっていくことを考えました。こうして地域にフィットすることによって、地域の台所になっていきます」

目次
地域にフィットするように変化していく
吉見氏の社会人生活は広告代理店勤務から始まったが、その後、食材の輸入や料理人のマネジメントに関わるなど食の分野に関わってきた。そこで課題として感じていたことは「食産業は生産性が低い」ということだった。そして、さまざまな産業ではDX化(ITの浸透が、人々の生活をより良い方向に変化させること)が進むようになり、「これらからの食はデリバリーが伸びていくのでは」と予測して、現在の事業に取り組むことになった。
会社を設立したのは2019年1月。2月に目黒区の住宅街にあるフード撮影スタジオ(5坪)を借り、営業許可を取得してスタート。ここから試行錯誤を重ね、変化をしながら7ブランドとなり月商500万円を売り上げるようにもなった。こうして「地域の台所」としての手応えをつかんだ。
2020年4月には株式会社トリドールホールディングスをはじめ3者から資金調達を行い、6月に西麻布に移転。以前と比べ3倍以上の広さとなり、前述のとおりブランドも増やした。
「Ghost Kitchens」は、スクエアな店内から外を見渡せるようになっている。厨房はドライキッチンでスタッフはきびきびと働いている。こうして「ゴーストレストラン」でイメージされる〝あやしさ″を完全に払しょくしている。同店を訪れるのはUber Eatsをはじめとしたデリバリーキャリアのほかに、テイクアウトをピックアップする一般のお客もいる。イートインスペースを持たないが、「地域の台所」として根差している。
吉見氏は、拠点づくりに際してマーケティングをしないことを主義としている。「特定したエリアで、年代や性別を捉えてモノをつくると、既存のものと似通ったものができてしまう」と考えるからだ。
大切にしている発想は「自分たちはこれが欲しい」ということ。その端緒が創業当時につくった「さらだのあるせいかつ」である。最近増えたブランドでユニークなものは「二日酔い食堂」。これは二日酔いのときに「シジミ出汁のお茶漬けを届けてもらえたら……」という発想でつくった。実際にここのメニューは土曜日の昼に一番出るようになっているという。

現状、西麻布の拠点では1日150食程度のオーダーがある。メニューは個食対応になっていて、ブランドによって多少の差があるが、新規客の場合1回のオーダーで2000円程度、リピーターで3000円近くになる(配送料はお客が負担)。
吉見氏は、「クリエイティブ」と「オペレーション」を明確に分けて考えていく。クリエイティブとはブランドの分野を考えてレシピをつくること。一方のオペレーションとは、調理をする、配送をするという部分だ。オペレーションの部分は今後ロボットテクノロジーが担うようになり、最終的にクリエイティブという人間の仕事が残る。これは「あいまいさ」でもあり、「発想」を最も大切にしている吉見氏ならではの事業観である。
吉見氏が目指す10年後の存在感は「フード分野のクリエイティブチーム」であり、店の中がロボットのみで、人がいないような状態をつくっていきたいとしている。これがクリエイティブとオペレーションの究極の形というものであろう。
「地域最適化」はリアル店舗のベーシックインカム
この事業の肝心なポイントは「地域最適化」である。これをゴーストレストレストランの形でリアル店舗にとってのベーシックインカム(基本所得)と位置付けたいと考えている。
「既存の飲食店は箱ものビジネスなので、客単価×回転数×席数で回していき、そのピークがくると売り上げはそれ以上になることができない。それを超えられるものがゴーストレストランなのです」
「地域で求められる飲食店は、人口動態や流行によって変化していくもので、その変わり続けるものをいかにしてわれわれのクリエイティブでPDCAを回していくか、ということがわれわれの役目です」
「家の周りに10店しか店がないけれども、それぞれの飲食店がゴーストレストランを1つずつ手掛けると、お客様にとっての選択肢は20になる。選ぶものが増えることは、食の楽しさを豊かにすることです」

このような発想をもとにして、現在の事業ではFCパッケージを準備しつつある。
筆者は「これからリアル店舗はどのような存在になると思うか」と吉見氏に尋ねた。
吉見氏は「リアル店舗は必要です。お客様はリアル店舗があると信用します」と前置きしてこう述べた。
「これまでの飲食店の方向性は『いかに席数を増やすか』というところにありましたが、これからは逆の方向、『いかにキッチンを広くするか』に進みます。席は、売上を上げる場所ではなく、体験を提供する場所になっていく。そこでお客様に体験してもらって、最終的な購入はwebで行ってもらうという形。リアル店舗はエンターテインメントであり、ブランドを感じる場所です」
「例えば、店の中に5席しかなくても、そこでの体験がものすごく素晴らしい、価値の高いものと感じられたら、それを体験した人や、来店できない人がこの店の商品をオーダーします。こうなると、一つのリアル店舗がつくり上げる売上よりも高いものになることでしょう」
起業家に必要なのは「未来を引き寄せる力」
多くの人々は今日ほどデリバリーが隆盛するとは想像していなかったのではないか。
その理由は、日本は国土が狭いし、コンビニがたくさんある。そんな環境の中で、お金を多めに払ってデリバリーを頼む人はマイナーなのではないか、という具合である。しかしながら、今ではデリバリーアプリが目出つようになった。
「お客様は便利な方を買います。テイクアウトよりも価格が1.5倍になっても買う。でもこの仕組みが価格破壊になるタイミングがある」
このように語る吉見氏の読み方はこうだ。
これからデリバリーを取り巻く環境は激しく変化していく。まず、デリバリーキャリアの価格競争による配送料のディスカウント。そして、配送機能の自動運転化。これも登場してからしばらくすると手軽に利用できることになる。
そして「医食同源」、人々の興味はヘルスケアに向かっていく。
「すると料理は音楽のような存在になっていくことでしょう。料理を作ることそのものは楽しい。それは自己表現だから。一方で、自分の健康管理を考えた場合の料理は、価格的に日常的なものに近づいていくと、自分で作ることはナンセンスと思われるようになるのでは。私たちはこのような時代になるためのサービスをつくっていきたい」
吉見氏はこのような論理をよどみなく語る。新型コロナ禍になる1年前までははるか未来のことのように考えられていたが、今や現実味を帯びている。吉見氏の談話から、今日の起業家にとって、いわば「未来を引き寄せる力」というものが必須条件となっているのではないかと感じた。

【関連記事】
ー連載 「ゴーストレストラン」が飲食業にもたらす価値とは? 第2回 TGAL(東京・千代田区)ー
ー連載 「ゴーストレストラン」が飲食業にもたらす価値とは? 第1回 夢笛(広島・福山)ー
店舗情報
店舗名 / 会社名 |
株式会社ゴーストレストラン研究所 |
|---|---|
業態 |
フードデリバリーサービスの提供「Ghost Kitchens」「すーぷのあるせいかつ」「さらだのあるせいかつ」「きょうだけゆるして」「ふるーつ宅急便」「二日酔い食堂」 |
開店・設立日 |
2019年01月07日 |
住所 |
東京都港区西麻布2-25-31クオーレ西麻布 |
公式サイト |
公式サイトを見る |