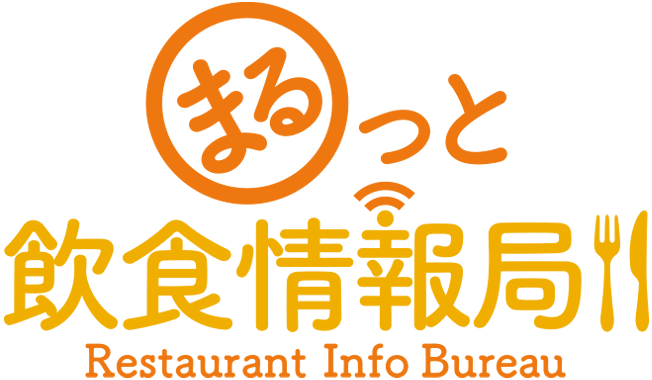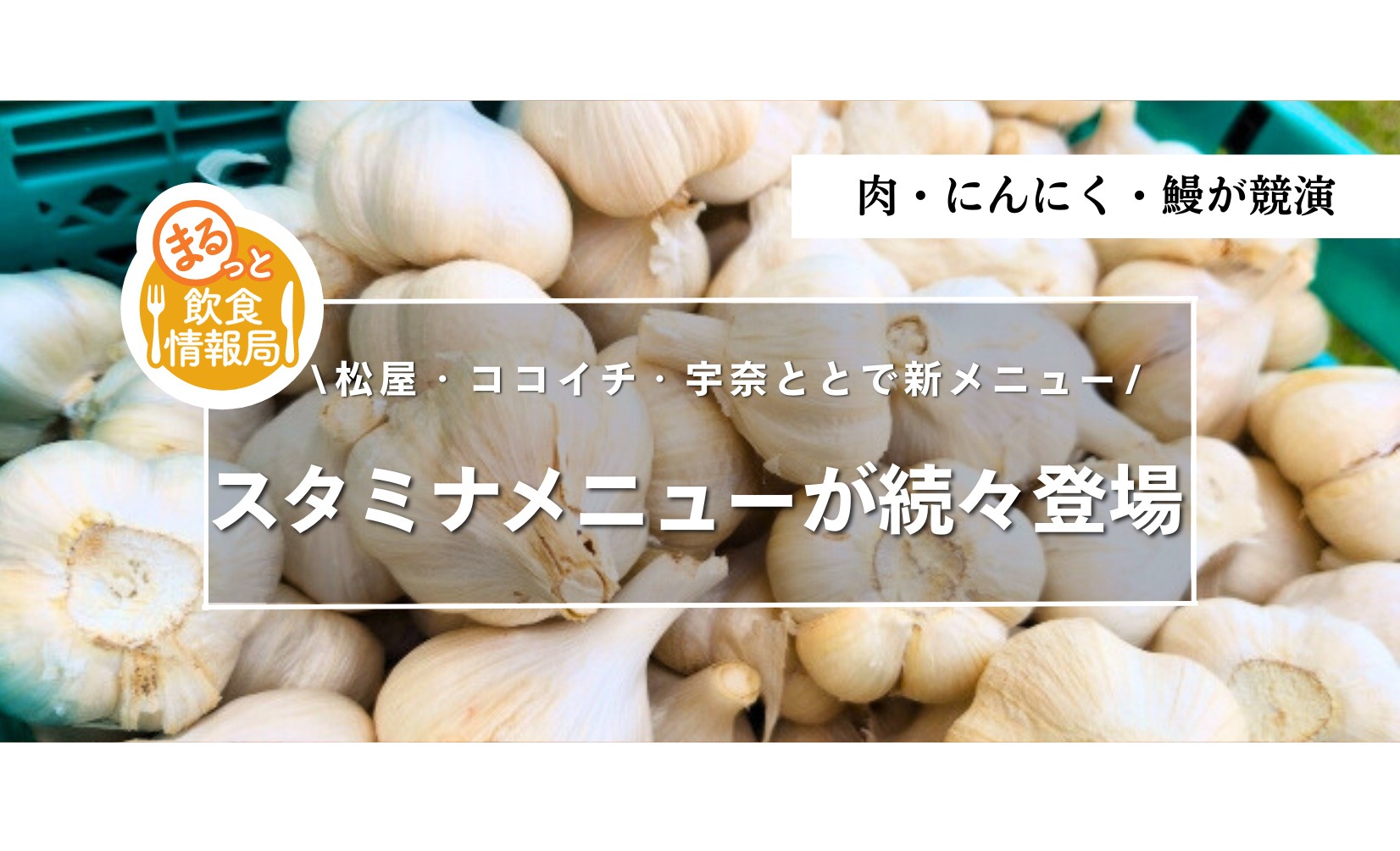在留資格ごとの在留期間更新のタイミングはいつまで?有効期限や更新許可申請方法を解説
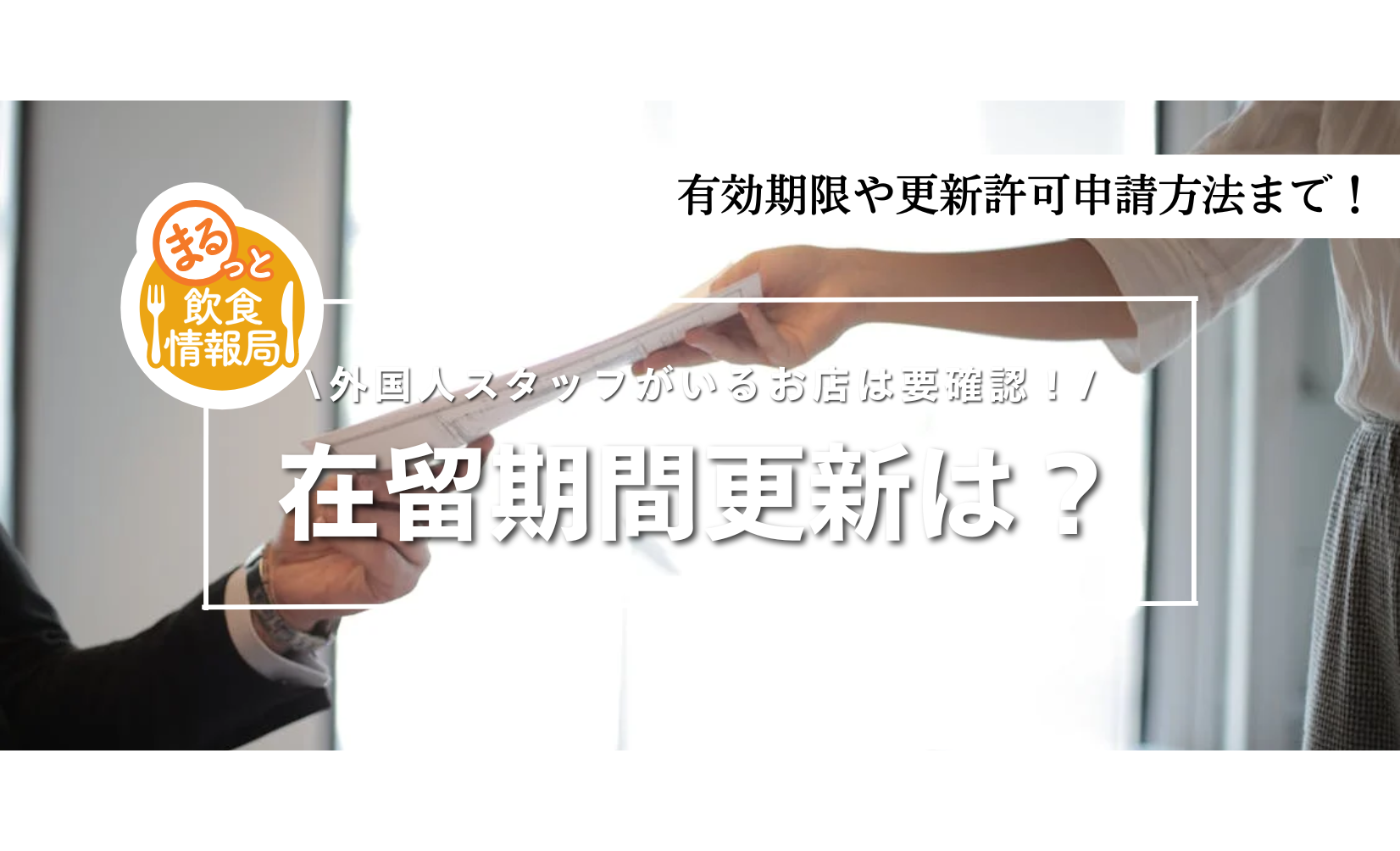
自社の人材不足の解消のため外国人人材の活用は有効な手段ですが、外国人社員を抱える経営者の方で、以下のようなお悩みはありませんか?
「各在留資格の更新時期がよくわからない」
「更新手続きの流れや必要書類が把握できていない」
「更新が認められず、社員が離職するリスクが心配」
本記事では、在留資格ごとの更新タイミングや有効期限、更新許可申請の具体的な方法などを詳しく解説しています。
本記事を最後まで読めば、外国人社員の在留資格管理に関する知識が深まり、トラブルを未然に防ぐための備えができるはずです。
優秀な外国人人材に長く活躍してもらうためにも、本記事をぜひ参考にしてください。
なお、弊社G-FACTORY株式会社では、飲食業界の人材不足を解消するため外国人人材の採用支援から就労者の在留資格・特定技能ビザ取得支援、労務管理の整備など企業側の受入支援まで外国人人材の採用サポートを一気通貫で行っています。
自社の飲食店で、外国人材による人材不足の解消を図りたいと検討している方は、以下のページからお気軽にご連絡ください。

日本での在留資格とは?
在留資格とは、外国人が日本で活動するための法的な地位を指します。留学、技術・人文知識・国際業務、特定技能など、在留目的に応じて29種類に分類されています。
在留資格は、外国人が合法的に日本に滞在し、各資格で定められた活動を行う上での基盤となるものです。
また、資格ごとに許可される活動内容や在留期間が異なるため、適切な資格の取得・更新が求められます。
なお、在留資格は一般的に「ビザ」と混同されがちですが、ビザは入国許可の推薦状に過ぎません。
在留資格は、ビザとは異なる概念であるのを理解しておきましょう。
また、在留資格の詳細に関して、以下の記事で分かりやすく解説しています。在留資格を体系的に理解したい方は、ぜひご一読ください。
在留資格の完全ガイド|29種類の一覧・就労可否・取得方法を徹底解説!
在留期間とは
在留期間とは、外国人が在留資格に基づいて日本に滞在できる期間を指します。在留期間は在留カードに明記され、永住者以外の外国人には在留期間の制限が設けられています。
在留期間が満了すると、更新手続きを行わない限り不法滞在なので、長く雇用したい場合はしっかり更新するようにうなさなければなりません。
また、不法滞在者には懲役や罰金などの厳しい罰則が科されるうえ、国外退去を命じられる可能性もあります。
原則として在留期間満了日の3か月前から申請可能ですが、在留資格や個別状況によっては前倒し申請ができない場合もあります。詳細は出入国在留管理庁への確認を推奨します。
通常、2週間から1ヵ月で審査が完了し、必要書類の提出と手数料の納付を経て、新しい在留カードが交付されます。
在留カードとは
在留カードは、中長期間日本に滞在する外国人に発行される身分証明書です。在留資格や在留期間を証明する重要な役割を担っています。
カー ドには以下の外国人の身分事項が記載されています。
-
• 氏名
-
• 生年月日
-
• 国籍
-
• 住居地
-
• 在留資格
-
• 在留期間など
16歳以上の外国人の在留カードには顔写真が表示され、公的な身分証明書でも使用可能です。
また、在留カードにはICチップが搭載されており、偽造防止と情報の電子的管理に対応しています。
ただし、外国人はカードに記載された情報に変更があった場合、速やかに出入国在留管理庁への届け出を出さなければなりません。
在留期間と在留カードの有効期限の違い
在留期間と在留カードの有効期限は密接に関係していますが、同義ではありません。
在留期間は、外国人が各在留資格で日本に滞在できる法的な期間を指します。在留カードの有効期限はカード自体の更新が必要な期間で、両者の期間は一致しています。
ただし、永住者や高度専門職2号などの一部の在留資格では、在留期間の制限がない代わりに、7年ごとに在留カードの更新が必要です。
また、16歳未満の外国人の在留カードは、16歳の誕生日か在留期間の満了日のいずれか早い方が有効期限なので注意しましょう。
在留期間が切れた場合は不法滞在にあたりますが、在留カードの有効期限が切れただけでは、不法滞在とはみなされません。しかし、身分証明書の効力は失われるため、速やかに更新手続きを行うよう伝えるようにしてください。
反対に、在留カードの有効期限が残っていても、在留期間自体が満了していれば不法滞在となるため、在留期間の更新管理が最重要です。
【29種類】在留資格ごとに在留期間の更新が必要な有効期限
在留資格ごとの在留期間と、更新のタイミングをまとめました。適用される在留資格を確認し、更新時期を見逃さないよう注意しましょう。
|
在留資格 |
有効期限 |
|
外交 |
外交活動の期間 |
|
公用 |
5年、3年、1年、3月、30日、または15日 |
|
教授 |
5年、3年、1年、または3月 |
|
芸術 |
5年、3年、1年、または3月 |
|
宗教 |
5年、3年、1年、または3月 |
|
報道 |
5年、3年、1年、または3月 |
|
高度専門職1号 |
5年 |
|
高度専門職2号 |
無期限 |
|
経営・管理 |
5年、3年、1年、6月、4月、または3月 |
|
法律・会計業務 |
5年、3年、1年、または3月 |
|
医療 |
5年、3年、1年、または3月 |
|
研究 |
5年、3年、1年、または3月 |
|
教育 |
5年、3年、1年、または3月 |
|
技術・人文知識・国際業務 |
5年、3年、1年、または3月 |
|
企業内転勤 |
5年、3年、1年、または3月 |
|
介護 |
5年、3年、1年、または3月 |
|
興行 |
3年、1年、6月、3月、または30日 |
|
技能 |
5年、3年、1年、または3月 |
|
特定技能1号 |
法務大臣が指定する期間(1年以内) |
|
特定技能2号 |
3年、1年、または6月 |
|
技能実習1号 |
法務大臣が指定する期間(1年以内) |
|
技能実習2号 |
法務大臣が指定する期間(2年以内) |
|
技能実習3号 |
法務大臣が指定する期間(2年以内) |
|
文化活動 |
3年、1年、6月、または3月 |
|
短期滞在 |
90日、30日、または15日以内の日数 |
|
留学 |
法務大臣が指定する期間(4年3月以内) |
|
研修 |
1年、6月、または3月 |
|
家族滞在 |
法務大臣が指定する期間(5年以内) |
|
特定活動 |
5年、3年、1年、6月、3月、または法務大臣が指定する期間(5年超える場合あり) |
|
永住者 |
無期限 |
|
日本人の配偶者など |
5年、3年、1年、または6月 |
|
永住者の配偶者など |
5年、3年、1年、または6月 |
|
定住者 |
5年、3年、1年、6月、または法務大臣が指定する期間(5年超える場合あり) |
在留資格ごとの在留期間の更新方法
在留期間の更新とは、現在の在留期間を延長して、引き続き日本に滞在できるようにするための手続きです。
在留期間の更新にあたっては、以下の手順を踏む必要があります。
-
• 在留期間更新許可申請
-
• 申請期間の確認
-
• 必要書類の準備
-
• 申請方法の選択(地方出入国在留管理官署またはオンライン)
-
• 申請にかかる時間の把握
-
• 手数料の納付
それぞれの手続きを詳しく見ていきましょう。
在留期間更新許可申請
現在の在留期間を延長するための手続きを「在留期間更新許可申請」と言います。入管法第21条に基づき、法務大臣の許可を得る必要があります。
所定の申請書類を揃え、指定された方法で提出しましょう。
審査基準に基づいて継続的な在留の適否が判断され、許可が下りれば、手数料を収入印紙で納付できます。
また、在留期間更新許可申請は、在留期間が終わりを迎える3ヵ月前より行えます。
そのため、外国人労働者の方に前もってアナウンスし、ゆとりを持って更新許可申請できるようにしていきましょう。
申請期間
原則、在留期間の更新許可申請の受け付けが開始されるのは、在留期間が終わる3ヵ月前です。3ヵ月よりさらに前からの申請も可能ですが、特別な事情がある場合に限ります。
また、在留期間満了日前に随時申請ができるケースがあり、6ヵ月未満の在留期間に該当する方のみ可能です。
ただし、病気や大けがなどでの入院や出張など、特別な事情がある場合は、出入国在留管理庁に事前に相談をしなければなりません。
必要書類
在留期間の更新申請には、在留資格に応じた各種書類の提出が必要です。
申請人の在留活動を証明する資料が求められる場合が多く、勤務先からの書類や、活動内容を示す資料の準備が欠かせません。
代理人が申請を行う場合は、申請人との関係を証明する書類の添付も必要です。
また、疾病での在留期間の更新など、特別な事情がある場合は、診断書や理由書の提出が求められる場合があります。
在留期間更新許可の申請方法は2つ
在留期間の更新許可は、以下2つの方法で申請できます。
-
• 地方出入国在留管理官署での申請
-
• オンラインでの申請
それぞれの申請方法を解説します。
地方出入国在留管理官署での申請
多くの場合、管轄の地方出入国在留管理官署窓口で更新手続きが行われます。
窓口の受付時間は、平日の午前9時~12時、午後1時~4時です。一部の手続きは曜日や時間が指定されている場合があるため、事前に確認するようにしましょう。
また、在留資格によって提出先や手続きの内容が異なる場合もあります。
申請でつまづかないために、管轄の地方出入国在留管理官署や外国人在留総合インフォメーションセンターに相談し、正確な情報を入手するようにうながしてください。
加えて、一部の地方出入国在留管理官署では事前予約制を導入しています。最寄りの官署の予約受付状況を確認し、計画的に手続きを進めるようアナウンスしていきましょう。
参考:東京出入国在留管理局申請予約システム|出入国在留管理庁
オンラインでの申請
外国人本人の場合、マイナンバーカードを利用したオンライン申請も行えます。
申請できる在留資格や手続きの内容は、事前にオンラインでの確認をするようにうながしていきましょう。
また、システムメンテナンスなどで利用できない時間帯もあるため、余裕を持ったスケジュール管理が求められます。
さらに、弁護士や行政書士、所属機関の職員などが代理でオンライン申請を行う場合は、あらかじめ出入国在留管理庁からの認証を受けなければなりません。
なお、オンライン申請の手順に関しては、出入国在留管理庁が詳しい操作マニュアルやQ&Aを提供しています。
申請にかかる時間
在留期間更新許可申請の標準処理期間は、2週間から1ヵ月です。
提出書類に不備がなく、審査に必要な情報が過不足なく揃っている場合は、比較的スムーズな手続きが期待できるでしょう。
ただし、窓口の混雑状況や、追加の事実確認が必要なケースでは、審査に時間を要する場合があります。
余裕を持ったスケジュールを立て、必要に応じて窓口に進捗を確認するようにしてください。
手数料
在留期間更新許可申請が通った場合、収入印紙4,000円分の納付が必要です。
収入印紙は、申請書に貼付して提出します。なお、申請が不許可の場合でも、納付済みの手数料は返還されないため注意しましょう。
なお、手数料納付書は、あらかじめ出入国在留管理庁のWebサイトからダウンロードできます。
在留期間の更新を行わなかった場合
在留期間の更新手続きをせずに在留期限が過ぎた場合、不法滞在者に該当してしまいます。
不法滞在は出入国管理および難民認定法第70条に該当し、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、あるいはその両方が科せられる可能性があります。
また、退去強制処分の対象で、最長で5年間、日本への再入国が禁止されるのも注意しなければなりません。
ただし、以下2つのケースでは、特例措置や救済措置が設けられています。
-
• 在留期間更新の審査中に有効期限が切れた場合
-
• 在留期間の更新がなされずに有効期限が切れた場合
それぞれのケースに関して、以下で解説します。
在留期間更新の審査中に有効期限が切れた場合
在留期間更新の審査が完了するまでの2ヵ月間は、更新の審査期間で在留期限を迎えてしまっても特例的な在留が認められます。
特例期間中、在留カードの裏面に「更新手続中」の押印がなされるため、在留資格の確認が必要な場面で提示できます。
更新が許可された場合は、特例期間内に新しい在留カードが交付されますが、不許可の場合は速やかに出国しなければなりません。
特例期間は、あくまで更新手続きを行っているのが前提の制度です。更新申請を行わないまま在留期限を徒過した場合は、特例の対象外なので注意してください。
在留期間の更新がなされずに有効期限が切れた場合
在留期間が終わって、更新手続きを行わずに在留を続けると、不法滞在に該当し上述の罰則規定が適用されます。
ただし、うっかり期限を徒過してしまった場合など、故意ではない短期間の不法滞在に関しては、一定の救済措置が設けられています。
出入国在留管理庁への事情説明と適切な手続きを速やかに行えば、在留期間の更新が特別に認められる可能性があります。
ただし、救済措置はあくまで例外的な取り扱いであり、常に認められるわけではありません。在留期間の更新は、必ず満了日までに行うのが原則です。
在留資格ごとに期間更新の有効期限を会社内でも確認しよう!
社員の在留資格管理は、外国人を雇用する企業の重要な責務です。各在留資格の制度や更新手続きを正しく理解しておきましょう。
また、在留期間の更新手続きは外国人労働者が行わなければなりませんが、企業側も在留資格の確認を怠ってはいけません。
在留カードや旅券、雇用契約書などの確認を通じて、社員の在留資格と在留期限を常に意識しておきましょう。
なお、弊社G-FACTORY株式会社では、飲食業界の人材不足を解消するため外国人人材の採用支援から就労者の在留資格・特定技能ビザ取得支援、労務管理の整備など企業側の受入支援まで外国人人材の採用サポートを一気通貫で行っています。
自社の飲食店で、外国人材による人材不足の解消を図りたいと検討している方は、以下のページからお気軽にご連絡ください。