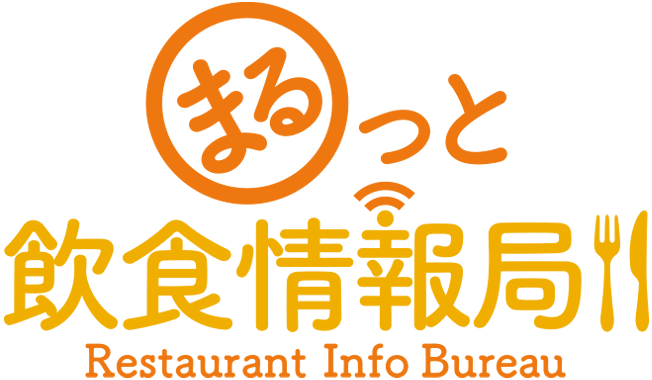2019/07/01
外務省官僚がタイ料理に魅了され起業、オンリーワン企業に躍進

「元外務省官僚のフードサービス業経営者」というと、「異色の……」という枕詞をつけて語り出すものかもしれないが、その人物である株式会社SUU・SUU・CHAIYOO(以下、SSC)代表取締役の川口洋氏は、お堅い前職のイメージは微塵もなく、天真爛漫に事業に取り組んでいるように見受けられる。ちなみに、社名であるSSCとは「頑張れ・頑張れ・万歳」とう意味だそうだ。現在、東京都下にタイ料理店を15店舗、タイのバンコクに1店舗展開している。

川口氏は1969生まれ、兵庫・宝塚出身。海外に関わることに興味を抱くようになったきっかけは、学生時代に体験した海外旅行であった。飛行機の中やヒッチハイクした車の中で現地の人たちとコミュケーションを取るのがとても楽しかったという。
目次
思いがこもった旗を揚げると人が集まってくる
外務省時代はアラビア語の専門家として活躍、中東のシリア、オマーンに駐在した。オマーンの当時、大使館の中で催す食事会で日本料理で接待をするため日本料理食材を求めてタイに買付けに行く機会があった。そこで、現地のタイ料理店を体験していくうちにタイ料理に魅了されるようになったという。
官僚として忙しくも楽しい日々であったが、だんだんと「何か自分で商売がしたい」という思いが募っていった。そして実際に辞める段になった時には、「タイ料理の飲食店で独立する」ということを決意していた。
そこで、タイ料理を展開している株式会社スパイスロードで修業することを志願した。
スパイスロードでは主に新橋店で修業し、この店の味を好ましく感じていた。当時「ベンチマーク」という意味を知らなかったが、さまざまなタイ料理店を食べ歩く中で自分が思い描くタイ料理店の方向性が定まっていった。川口氏が好みのタイ料理の食味は、「タイの田舎の店で親父さんが調理している濃い味」だそうだ。同社には約10カ月在籍した。
タイ料理店を開業するためにはその分野のシェフが必要となる。これらのことをどのように考えていたのだろうか。
「修業している店や出会う人に『タイ料理店を開業したい』と思いを語り掛けたところさまざまな人が、人材や不動産、ビールメーカー、酒販店などいろいろな情報を教えてくれました」
当時を振り返って川口氏は「思いがこもった旗を上げたら人が集まってくる」という感じだったという。
このように縁がつながっていくうちに、川口氏はタイ人の間で「タイ料理店を開業準備中の人物」として知られるようになった。タイ食材を扱う小売店で商品を探していると、同店を訪れていたタイ人から「何か仕事はありませんか」と話しかけられたり、「知人の友だちの友だち」という覚えのないタイ人から電話がかかってくることもあった。

“動物的な本能”で出店することがベスト
1号店の「クルン・サイアム」は2004年9月、自由が丘に出店した。物件は「飲食店.com」で探し出した。ここに決めるまでに、100件、200件という数多くの物件を見たが契約に至らず、さらに過去物件を見ている中で探しあてた。「少し値段が高いけど、まあここで決めよう」という感覚で決断した。
その後の物件は、自分がやってみたいと思ったところで店舗展開をしていった。物件を探し当てる経験を踏まえて、川口氏としてのその哲学が醸成されていった。
「人間には“動物的な本能”と“人間的な衝動”があります。店舗物件を探す場合、私としては“動物的な本能”で決めることを大事にしていて、純粋に自分たちが出店したい、行きたい、働きたいと思う場所で出店するようにしています。“人間的な衝動”とは『この場所で商売をやればカッコイイ』『ここだったら儲かりそうだ』という具合に自己重要感を満たそうとする気持ちやよこしまな気持ちが入り込むと他と比較して相対的にしか幸せを感じられなくなり不幸な気がします。この点は出店先の決定のみならず生きていくうえで気を付けていることです」
店名にはどのような思いが込められているのか。
最初の店名「クルン・サイアム」は、「クルン」とはタイ語で「古い都」、サイアムはタイ王国の旧称である。そこで、川口氏は20世紀初頭に建てられた外交官や商社マンが住む異人館の中でお客様をおもてなしする、ということをイメージした。それをさらに分かりやすくお客様に伝えるために「オールドタイランド」という店名をつけた。
2014年6月、レシピを再構築するために「タイ料理研究所」をつくった。本社のある東京・駒場に小さな物件を借りてそこで研究を重ねていたが、お客様が研究所であることにお構いなくい入店するようになり、そこを店として営業するようになった。4坪に満たない店であったがランチで50人が入るという繁盛店であった。同店はその後知人に譲渡した。

タイ本国に出店したことで雇用や仕入れの拠点となる
タイ現地には2017年2月に出店した。タイに店があることによって、日本の店で働いている人のモチベーションが高くなった。
人材面では、タイの店で現地の人に働いてもらい、その後日本に来てもらうという雇用のパターンで2年間に15人ほどが日本にやってきた。
同店は、現地のものを買い付ける拠点にもなっている。店の中の重要な装飾品となっているトゥクトゥクも既に5台購入している。
川口氏はこう語る。
「タイに店を持つことは念願でした。いつまでにつくるかという計画的なものではありませんが、出店してみるととても楽しい。これは自己満足ではなく、『タイに出店したら皆が楽しいだろうな』という発想でした。すると結果うまくいったということです」
タイでは同店を起点に店舗展開することを想定している。
「海外で本格的に店舗展開をするのはアメリカです。ロサンゼルスから展開していくイメージは、お客様が最初にボウルを持ち、最初にご飯を入れてもらい、その後好みの具材を次々とトッピングしてもらい、ボウルの商品を完成させるというもの。アメリカでタイ料理店をチェーン展開していくというのは私の代だけではなく、二代三代と世代を超えて取り組んでいこうと考えています」
タイ食材の流通を手掛け、メーカー機能も想定する
川口氏はタイ料理店にとって重要な商材である米麺を自社でつくろうと考えている。現在、タイから自社ブランドのジャスミンライスを輸入していて、「SUU SUU RICE」という名称で広めており、この米で製麺を検討している。
日本での店舗展開は、1年に3店舗ペースの計画を立てており、都心がメインとなって行く模様。また、SUU SUU FOODSという食品会社をこの5月に設立したばかりで、ここで食品の輸入からメニュー提案を行っていこうと考えている。
現状、ソースなどタイ料理のベースとなるものはタイの委託工場での製造に挑戦しているが、現状、うまく行っているとは言えず、日本で今期中にCKをつくって管理を徹底して食味を向上させ、そして、この事業をSUU SUU FOODSにつなげようと考えている。これらの取り組みは、店舗段階での労働時間を短縮化し、労働環境を整えていく狙いもある。
採用では新卒採用が定例化し、日本人タイ人をと問わず例年4~5人を採用。中途採用は、ホームページを見たり、紹介等で入社をしてくる。アルバイトはタイ人の従業員の紹介で入社してくる。
これらによって同社の従業員200人の中に占めるタイ人は8割近くになっている。社員は70人程度で社員比率が高い。社員比率が高いことから従業員の休暇が取りやすくなっている。
川口氏は、従業員と歓びを分かち合うことを大切にしている。そのために親睦の機会を務めて設けており、毎回160人程度が集まり参加率が高い。また、教育・研修を充実させ、年商の2%をそれに充てている。
競合を意識しないで店舗運営ができる
川口氏にとって現在の事業は純粋に「タイ料理が好きだ」ということがきっかけである。それが多店化することで、他の業種を展開すること異なる特徴はどのようなものだろうか。それについて川口氏はこう語る。
「タイ人の国民性は『今を楽しむ』という感覚で、自己重要感が自分の中で達成されています。日本人の従業員も、他の会社や店と比較して応募してくるのではなく、『自分はタイ料理が好きだ』という自分の価値観を持ってやってくる。こういう意味では、競合店を意識した店舗運営を必要としていない」
「われわれの経営理念は、『タイ料理の普及を通じての社会貢献』。自分たちが好きなタイ料理をたくさんの人に食べてもらうことで自分たちも周りも幸せになる。その観点からタイ料理ファンを増やすために多店舗展開を進めています」
「隋処作主」――「隋処に主となる(ずいしょにしゅとなる)」と読むというこの言葉は、禅宗の格言で「いつどこにあっても、如何なる場合でも何ものにも束縛されずに、真実の自己として行動する」という意味だ。まさにそのとおりの価値観を持っているタイ人に学びながら、川口氏は社業を進めていきたいとしている。


今回取材をした場所は、この3月東京ドームシティの1階に出店したばかりの「タイ料理研究所」である。同じタイミングで東京ドームの中にタイ料理の物販店をオープンし、東京ドーム内の食のバラエティを広げた。
川口氏は「東京ドームにはタイ料理を知らない人がたくさんいらっしゃいます。そういう方々に何とか食べていただく努力をし、食べた結果満足していただきたい。そのような環境で出店してみたかったし、タイ料理の可能性が見えてくる」と語り、これからの事業の広がりを画策している。