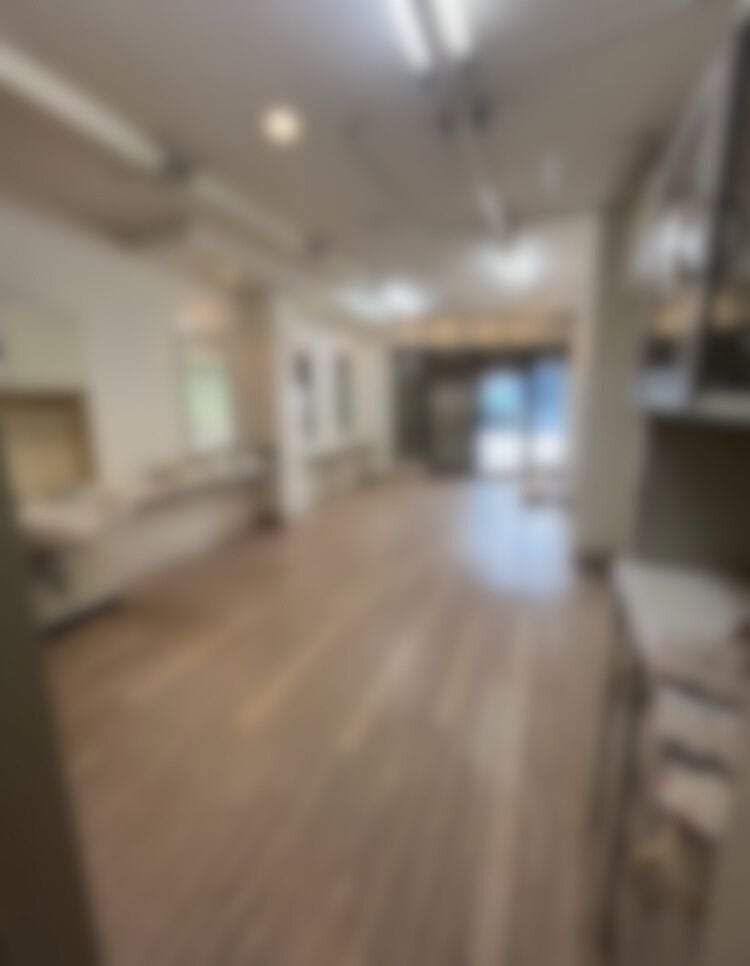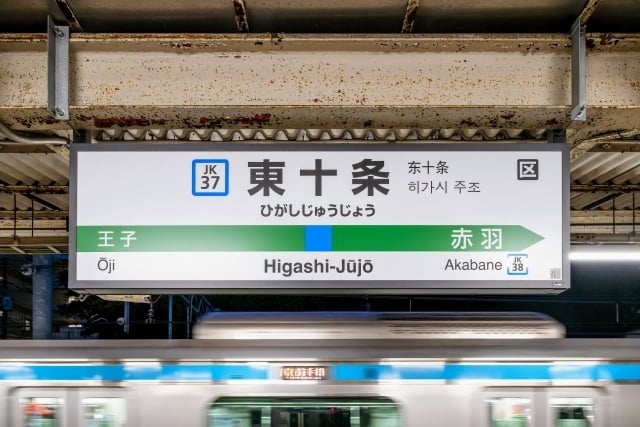フードロス削減の切り札となるか?飲食店とフードバンクの連携が生み出す未来とは

私たちの倫理観が問われる時代 ― 「食品ロス」問題の深刻さを考える
世界では飢餓に苦しむ人がいる一方で、日本では年間約522万トンもの食品が廃棄されています。(令和2年度推計値)
これは、日本人1人当たりに換算すると、毎日お茶碗約1杯分の食べ物を捨てている計算になります。飲食店を営む私たちにとって、この数字は決して他人事ではありません。
食品ロスは、環境問題、経済問題、倫理的な問題など、様々な側面から深刻な影響を及ぼします。

- 環境問題への影響: 食品の生産、加工、輸送には大量のエネルギーや資源が使用されています。廃棄されるということは、これらの貴重な資源の無駄遣いになるだけでなく、地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出にも繋がります。
- 経済的な損失: 廃棄される食品には、生産、加工、流通にかかったコストが全て無駄になります。飲食店にとっては、食材費の損失だけでなく、廃棄にかかる費用も大きな負担となります。
- 倫理的な問題: 食べ物を無駄にするという行為は、食料を必要とする人々に対する倫理的な問題を引き起こします。
飲食店は「食」を扱う企業として、食品ロス問題に対して積極的に取り組む責任があります。
その有効な手段の一つとして注目されているのが、「フードバンク」との連携です。
「フードバンク」:食品ロスを「食のセーフティネット」へ
フードバンクとは、企業や個人からまだ食べられる食品を寄付してもらい、生活困窮者や福祉施設などに無償で提供する活動、またはそれを行う団体のことです。日本では2000年代初頭から活動を本格化させ、現在では全国に約100のフードバンク団体が存在します。
フードバンクは、食品メーカー、小売店、飲食店などから、賞味期限間近やパッケージの破損など、まだ食べられるにも関わらず廃棄されてしまう可能性のある食品を無償で譲り受けます。そして、集めた食品を、必要とする福祉施設や団体、個人へ無料で提供しています。
飲食店がフードバンクと連携するメリットとは?
フードバンクへの食品提供は、単なる社会貢献活動にとどまらず、飲食店側にも多くのメリットをもたらします。
1. 食品ロス削減によるコスト削減効果
フードバンクに提供することで、廃棄費用を大幅に削減できます。廃棄量を減らすことは、食材の購入量を見直すきっかけにもなり、長期的なコスト削減に繋がります。
2. 企業イメージの向上、ブランディング効果
社会貢献活動への積極的な姿勢は、企業イメージの向上に大きく貢献します。特に、環境問題や社会問題に関心の高い消費者層からの支持を得やすく、新規顧客獲得や売上向上に繋がる可能性も秘めています。
3. 従業員満足度・モチベーション向上
フードバンク活動への参加は、従業員の社会貢献意識を高め、仕事に対するモチベーション向上に繋がります。食品ロス問題への意識向上は、業務における意識改革にも繋がり、より効率的な店舗運営を実現できる可能性もあります。
4. 地域貢献による地域密着型経営の推進
フードバンク活動を通して、地域住民との繋がりを築くことができます。地域貢献は、新規顧客の開拓や常連客の増加に繋がり、地域密着型の経営を促進する効果も期待できます。
フードバンク連携による成功事例:飲食店の新たな可能性
実際にフードバンクとの連携を通じて、社会貢献と経営改善の両立を実現している飲食店の事例を見ていきましょう。
事例1:カフェの「フードロスランチ」
閉店前に残ってしまったサンドイッチやパンなどを詰め合わせ、お得な価格で提供する「フードロスランチ」を販売しているカフェがあります。この取り組みは、食品ロス削減と同時に新たな顧客層を獲得することに成功し、売上アップにも貢献しています。
事例2:レストランの「チャリティメニュー」
特定のメニューを設け、その売り上げの一部をフードバンクに寄付するシステムを導入しているレストランがあります。顧客は食事を楽しみながら社会貢献に参加できるため、好評を博しています。
事例3:居酒屋の「持ち帰りサービス」
食べ残しを減らすために、持ち帰り用の容器を提供したり、持ち帰りメニューを充実させたりすることで、フードバンクへの食品提供量を増加させている居酒屋があります。環境問題への意識の高まりを受け、顧客満足度も向上しています。
フードバンクとの連携を始めるためのステップ
フードバンクとの連携は、決して難しいものではありません。以下のステップを参考に、貴店でも検討してみてはいかがでしょうか?

- 自店の食品ロス状況の把握: まずは、どのような食材がどれぐらい廃棄されているのかを把握することが重要です。
- 連携可能なフードバンクの選定: 地域のフードバンク団体を調べ、提供可能な食品や条件などが合致する団体を選びましょう。
- フードバンク団体への連絡・相談: 連絡を取り、食品提供に関する具体的な方法や条件などを相談します。
- 食品提供開始: 取り決められた方法に従って、食品を提供します。
- 従業員への周知徹底: フードバンク活動への理解と協力を得られるよう、従業員への周知徹底を図りましょう。
フードバンク連携を後押しする助成金制度
フードバンクとの連携を検討する飲食店のために、国や地方自治体では様々な助成金制度が用意されています。
これらの制度を活用することで、初期費用や運営費用を抑えながら、スムーズにフードバンク活動を開始することができます。
例えば、東京都では「食品ロス削減に向けたフードバンク活動促進事業」を実施しており、フードバンク団体と連携し、食品の提供や受領を行う事業者に対して、設備導入費や運営費の一部を助成しています。
まとめ:フードバンク連携で、持続可能な飲食店経営へ
フードバンクとの連携は、食品ロス削減という社会課題の解決に貢献するだけでなく、飲食店にとっても多くのメリットをもたらします。
コスト削減、企業イメージの向上、従業員満足度の向上など、経営改善に繋がる様々な効果が期待できます。
飲食店専門の不動産会社である当社では、フードバンクとの連携を希望される飲食店様を全面的にサポートいたします。
物件探しから店舗運営のアドバイスまで、お客様のニーズに合わせた最適なソリューションをご提案いたします。
食品ロス削減と社会貢献を両立し、持続可能な社会の実現に貢献しませんか?フードバンク連携による新たな飲食店の可能性を、当社と一緒に探求しましょう。