2025/06/24
張瀟俊にインタビュー!鳥居くぐりに隠された「ブランド力」を創造する鍵とは?

いまの時代、飲食店の業態はあらゆるものが存在していて、「出尽くした」という印象さえ受ける。ここから頭一つ抜け出すためには何が必要か。その正解は誰にも分からない。しかしながら、新業態で、突然繁盛しているところが存在して、それが「いまどきの繁盛店」というコトになる。
その現象を示しているのが「鳥居くぐり」という居酒屋である。いま、東京・池袋、新宿、そして神奈川・横浜と3店舗営業している。店舗のハードは、店名通りに、鳥居をくぐって店内に入る形。そして、店内の中央にしめ縄をあしらった本殿のような設えがあり、客席は暖簾で区切ったテーブル席が配されている。ホールを担当する女性スタッフのユニフォームは巫女風の衣装。ずばり「神社」をイメージさせる空間だ。
そしてもう一つの大きな特徴は、「お通しのおでん」が「500円で食べ放題」ということ。
非日常的な空間と、お得感を訴求するフードメニューが、既存の居酒屋に対して圧倒的な差別化となっている。
メインの客層は30代から40代あたり。1人のお客よりも、グループで利用しているパターンが多い。お客の表情はみなとても明るい。「ここにいるのが楽しい」という感じだ。
同業態を運営しているのはエレガントエース株式会社(本社/東京都新宿区、代表/張瀟俊〈チョウ・ショウシュン〉)。アイキャッチの人物が代表の張氏(36歳)である。同社は2016年1月に設立されている。

エントランスは鳥居をくぐって入るイメージ
なぜ『鳥居くぐり』はヒットしたのか?張氏が語る飲食店経営のブランド戦略
張氏は、中国の上海で生まれ育ち、中学校に進む段階で日本にやって来た。それは、日本での永住権を取得して中華料理の料理人として働いていた父親の元で、家族一緒に住むためであった。
高校生となってから飲食業に親しむようになり、主として中華料理店でアルバイトを行なった。大学に進んでからは、アルバイトリーダーを任されるようになった。
大学卒業と同時に、かつてアルバイトをしていた新宿の飲食店を、友人と二人で業務委託の形で運営した。同店は50坪程度で月商1500万円を売り上げていたが、張氏たちが運営するようになってから1800万円を売り上げるようになった。そして、起業のための資金を蓄えた。
こうして、2016年にエレガントエースを設立。それ以来、時代の潮流を読んで飲食店をつくっていった。「肉バル」「もつ鍋」「焼肉」という具合に、人気の業種を1年に1店舗のペースで増やしていった。
そして、コロナとなった。このとき張氏と同じ上海出身で、オーストラリアで飲食業を展開する友人を日本に招いた。
この友人は、オーストラリアで「すし食べ放題」のお店を35店舗展開していた。中でも2021年からは20店舗を出店したという。張氏は、自分の事業もこの事業スタイルに倣う必要性を感じた。そのために「ブランド力」をつくろうと考えた。
エレガントエースが目指している事業とは「お客様に喜んでいただくこと」。
お客が外食に行くことのきっかけとは、「家ではできない体験を求めている」から。
このような外食を求めるペルソナは「30代から40代の働く人々」。
このようにして、同社が考える「ブランド力のある店舗」を組み立てていった。

ホールを担当する女性スタッフのユニフォームは巫女風
飲食店は“体験”で差別化──張氏が語る非日常空間と高級感の作り方
これを具体化していくために、張氏の人生観をアイデアとして取り入れた。
張氏は、例年のように京都を訪れる。その一番の目的は、張氏にとってのパワースポットである伏見稲荷大社を参拝することだ。本殿でお参りをして、その脇にある千本鳥居をくぐっていくと心が清められて、エネルギーが得られた気分になる。
伏見稲荷大社を参拝した後の楽しみは、贔屓にしている天ぷら店で食事をすること。この京都での二カ所の体験は、張氏にとって大切な非日常体験のルーティンなのである。張氏はこのような人生観を、新しい事業の「ブランド力」につなげていこうと考えた。
フードメニューについては、かねて「おでん食べ放題」を注目していた。そして、おでんを看板商品に掲げながら、「天ぷら」「刺身」といった不動の人気メニューを添えて、来店動機を高めようと考えた。
こうして、「主要客層が30代40代」「鳥居をくぐる神社の空間」「おでん食べ放題、天ぷら、刺身」という、「鳥居くぐり」のコンセプトがまとまった。
「鳥居くぐり」では、お客が席に着くと巫女姿の女性スタッフが応対して、お店のコンセプトを丁寧に説明する。ここで「居酒屋ではなく、『鳥居くぐり』という空間にやってきた」という気分になる。
お店の中央に、本殿をかたどったスペースがあり、ここに大きなおでん鍋が敷き詰められたような形で配置されている。ここが「500円のお通し」「おでん食べ放題」の厨房である。おでんは、最初の一皿に、お店側があつらえた8品ほどの盛り合わせを提供。それを食べ終えると、お客が自分で皿を厨房に持ってきて、好みのタネを皿に入れてもらう。
客単価は4000円あたり。一般的な居酒屋よりもワンランク高い設定である。
そのポイントの一つは、オーダーが「おでん食べ放題」に集中しないよう、「2ドリンク2フード」をお客にお願いしている。それは「鳥居くぐり」という非日常性を保つためにも必要な仕掛けである。高級感を演出するために、お客のタイミングを見計らって、布のおしぼりの交換を適宜行っている。

店内中央の本殿をイメージした厨房の中に大きなおでん鍋を用意
飲食業の新しいトレンドを生み出すイメージ
1号店の池袋店がオープンしたのは2023年8月、67坪120席の規模。2号店は新宿店で24年9月オープン、58坪110席の規模。3号店は横浜店で96坪160席の規模。出店している階は、それぞれ、地下1階、5階、5階となっている。「鳥居くぐり」が訴求していることは、パワースポットであり、非日常性であることから、お店は路面にある必要がない。
このように「鳥居くぐり」が放つ独特の魅力は、多くの人々に知られるようになった。池袋店、新宿店では月に5000人の来客数が定着。横浜店はオープンして2カ月足らずで月7000人のペースで推移している。池袋店、新宿店の存在が「ブランド力」を発揮しているようだ。
筆者が学生の当時、1970年代後半から80年代にかけて「大箱居酒屋」のブームがあった。それは、店の規模が50坪から100坪と大きく、個人客よりグループ客などの宴会を受け入れた。ドリンク、フードともに何でもある。客単価は2500円程度。週末になると、この業態に若者がこぞって集まった。
当時の「大箱居酒屋」が人気であった理由を考えると、若者にとって、勤め人が利用するような専門的で高度な居酒屋は、懐具合からしてなじめないが、クオリティはさておき、メニューは何でもそろっていて、手が届く客単価で、型苦しい雰囲気がないといった手軽さがポイントであったのではないか。
筆者は、この「鳥居くぐり」の人気ぶりを見て、50年前の「大箱居酒屋」的なポテンシャルを感じている。「鳥居くぐり」における、かつての「大箱居酒屋」との大きな違いは、「テーマ性の高さ」「手が届く高級感」「フードに対する満足度が高い」ということ。このような業態の在り方が、飲食業の新しい潮流になっていくのではないか、と考えている。

お通し500円、食べ放題」のおでんは、最初盛り合わせを提供
店舗情報
店舗名 / 会社名 |
京出汁おでんと旬菜天ぷら 鳥居くぐり 新宿店 |
|---|---|
業態 |
和食居酒屋 |
開店・設立日 |
2024年09月01日 |
最寄駅 |
新宿駅 |
アクセス |
徒歩2分 |
住所 |
東京都新宿区新宿4-1-9 新宿ユースビル 5階 |
営業時間 |
|
定休日 |
不定休または店舗による |
電話番号 |
03-5990-2323 |
公式サイト |
公式サイトを見る |



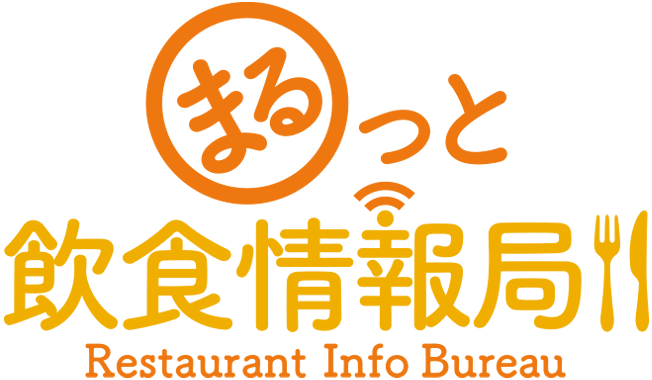



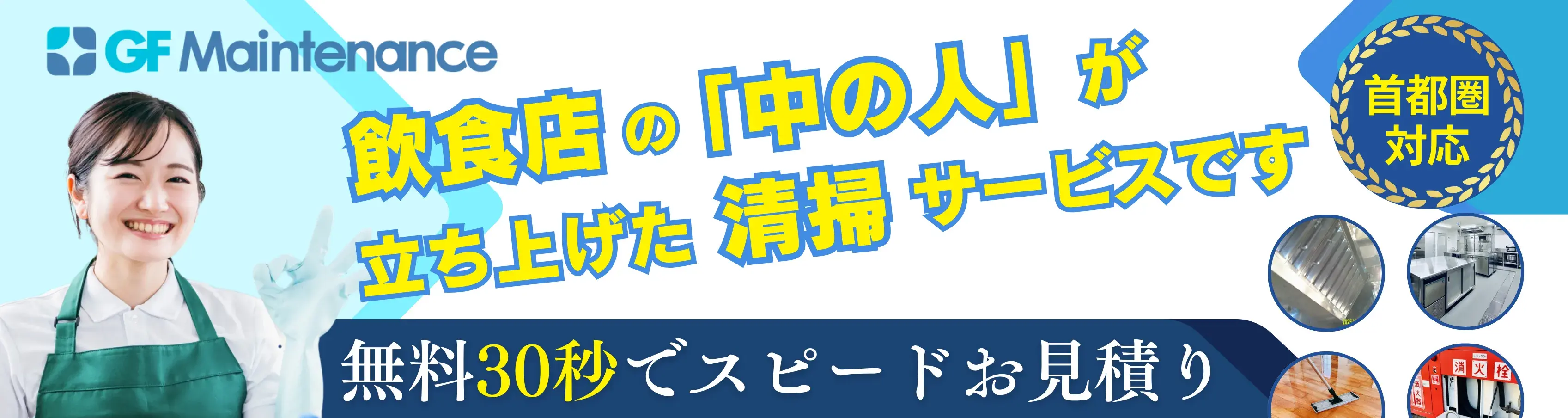
.png)
.png)
-1.png)
-1.png)
-1.png)

