2025/07/07
2026年の値上げは減速、それでも油断できない? 飲食店経営者が今考えるべきコストと価格戦略

2025年後半(7月〜12月)は、外食業界にとって「値上げラッシュの終わり」と「新たな価格局面の始まり」が交錯した期間だった。
帝国データバンクが公表する「価格改定動向調査」を月次で追うと、値上げ品目数はピークアウトし、2026年に向けて減速傾向が鮮明になった一方で、原材料高を中心としたコスト圧力は形を変えて残り続けていることが見えてくる。
本記事では、帝国データバンクの価格改定動向調査をもとに、2025年7月から12月までの動きを俯瞰しながら、外食・飲食店経営者がこの半年間で直面した変化と、そこから読み取れる次の経営判断のヒントを整理していく。
各月のデータはこちらから
2025年7月
値上げラッシュが再燃、調味料や菓子中心に2105品目が対象
株式会社帝国データバンクが2025年6月30日に発表した調査結果によると、2025年7月に予定される飲食料品の値上げは2105品目にのぼり、前年同月(418品目)に比べて実に5倍という急増ぶりを示している。この規模の値上げは2025年1月から7か月連続で前年同月を上回っており、2022年の「値上げ元年」とも言われた時期を超える勢いである。さらに8月には1,010品目が値上げされ、前年同月(661品目)から約1.5倍の増加を記録した。特に調味料が470品目と最多を占め、次いで乳製品が281品目となっており、物価上昇の波が広範囲に及んでいることが明らかとなっている。
とくに注目すべきは、調味料カテゴリの大幅な増加で、全体のうち実に1445品目が調味料に集中している。これはカレールウやスパイス、顆粒だし、液体だしなど、和洋中を問わず飲食業の基礎となる食材群が中心であり、原価への影響も極めて大きい。
一方、「菓子類」は196品目が値上げ対象となり、2025年3月以来4か月ぶりの高水準に。チョコレートやガム、スナック類など多様な製品で値上げが行われている。
また、「加工食品」では117品目が対象で、冷凍ごはん、パックごはん、パスタソースなど、主食や主菜に直結する製品が目立つ。
これらの動向は家庭用食品に留まらず、飲食店で使用される業務用商品への波及も避けられない。平均値上げ率は15%と、昨年の同時期(17%)よりやや下がってはいるが、依然として高い水準で推移している。
原材料高・エネルギーコスト・人件費が三重苦に
今回の値上げトレンドを読み解く上で、背景にあるコスト要因の複雑化が注目される。
調査によると、今回の値上げ品目の97.2%が「原材料価格の高騰」によるものであり、これは前月の98.0%からはわずかに減少したものの、依然として主要因である。
特に影響が大きいのは、小麦粉、食用油、米といった、主食・調理油の主要原料である。これに円安の影響も加わり、輸入コストの上昇が企業努力では吸収しきれない状況となっている。
また、「エネルギーコスト」の上昇も顕著で、全体の66.4%が電気・ガス代の増加を価格転嫁している。特に2025年に入ってからの中東情勢の緊迫化により、原油価格が再び上昇に転じており、原油が1バレル100ドルを超える水準に達した場合、2022年のような“原油連動型の値上げ連鎖”が再来するリスクもある。
さらに、人件費の上昇も深刻である。全体の53.9%の値上げ品目が、労務費の増加を要因としており、これは2023年以降の集計開始以来、最高の割合である。飲食業界では慢性的な人手不足が続いており、最低賃金の引き上げに伴う人件費増が避けられない構造となっている。特に中小規模の飲食店では、賃上げと食材コストのダブルパンチが経営を直撃している。
飲食店が取り得る選択肢とは:価格転嫁だけでは立ち行かない
こうした厳しいコスト環境のなか、飲食店がどのように生き残るかは、単なる価格転嫁にとどまらない創意工夫が求められている。
例えば、値上げされた調味料については、既製品の使用を見直し、店舗で手作りする自家製ドレッシングやソースに切り替えることで、コストコントロールとブランド価値向上を両立できる。また、メニュー全体の見直しも有効であり、ランチやセットメニューの構成を変更することで、実質的な値上げを感じさせずに客単価を維持するアプローチが注目されている。
さらに、内容量の調整や原材料の置き換えも一つの手段である。たとえば高騰している牛肉の代わりに、鶏肉や豆類を使ったヘルシーな新メニューを開発するなど、「コスト削減」と「健康志向」を同時に打ち出す施策は、現代の顧客ニーズにもマッチする。また、デジタルオーダーシステムやセルフレジの導入によるオペレーションの効率化も、人件費削減策として効果的であり、店舗規模にかかわらず導入の動きが広がりつつある。
〈食料品値上げへの具体的な対策例〉
・既製品の調味料から、自家製ソース・ドレッシングへの切り替え
・メニュー構成の再設計
・内容量の調整(ポーションコントロール)
・高騰食材の代替利用
・健康志向・新価値提案の同時訴求
・デジタルオーダーシステム/セルフレジの活用の導入
値上げラッシュ、累計2万品目突破 飲食業界に「持続可能な経営」模索の動き
飲食料品の値上げが止まらない。帝国データバンクがまとめた調査によると、2025年7月に実施された値上げは2105品目と、前年同月(418品目)の5倍に達した。8月も1,000品目超が続き、9月には1422品目を記録。11月までの累計は2万34品目となり、前年(1万2520品目)を大きく上回り、2年ぶりに「2万品目の大台」を突破した。専門家からは「インフレ定着の兆し」との声も上がる。
こうした中、飲食業界では価格変動リスクに対応するための経営モデル転換が急務となっている。原材料やエネルギーなど、店舗の努力だけでは吸収できないコスト要因が増す中で、調達先の多様化や地場産品の活用、さらにメニューを柔軟に入れ替える仕組みや「ダイナミック・プライシング」の導入など、新たな取り組みが注目され始めている。
急速に進む値上げトレンドの先にあるのは、「持続可能な飲食経営」をいかに実現するかという課題だ。
2025年10月
株式会社帝国データバンクがまとめた調査によると、2025年10月に予定される飲食料品の値上げは 合計3024品目 にのぼった。
前年同月(2924品目)から+100品目・+3.4%と10カ月連続で前年を上回り、連続増加期間としては統計開始以来、最長を更新した。
単月で3,000品目を超えるのは4月(4,225品目)以来6カ月ぶりであり、食品価格の上昇が再び勢いを取り戻しつつある。平均値上げ率は 17% と依然として高水準で推移している。
酒類・飲料が突出、焼酎・リキュール・日本酒が中心に
分野別では、焼酎やリキュール、日本酒などを中心とした 「酒類・飲料」 が最も多く、2262品目に達した。
このカテゴリで単月2,000品目を超えたのは、2023年10月(3,198品目)以来、2年ぶりのことだ。
「加工食品」も340品目が対象となり、包装米飯や餅などの主食系商品が中心に値上げされた。
また、「調味料」は246品目で、焼肉のたれや味噌製品が値上げの中心となった。
通年では2万381品目、前年を62.8%上回る
2025年通年では、12月までの公表分で 累計2万381品目 に達し、前年実績(1万2520品目)を 62.8%上回った。
2万品目を超えるのは2023年以来2年ぶりである。
食品分野別では「調味料」が6148品目と最多で、前年(1715品目)から+4433品目・+258%の急増。
次いで「酒類・飲料」(4871品目)が続き、ビール、清酒、焼酎、ワイン、清涼飲料など幅広い範囲で値上げが実施された。
平均値上げ率は通年で15%と、前年(17%)よりやや低下したが、依然として消費者の負担感は大きい。
値上げ要因は?原材料・物流費・人件費が重なる“三重苦”

今回の値上げの背景には、複合的なコスト上昇 がある。
最も多い要因は「原材料価格の高騰」で、全体の 96.1% に及んだ。
続いて「物流費」78.8%、「エネルギー(光熱費)」64.3%、「包装・資材」62.9%、「人件費」50.2%と、
主要コスト要因のほぼすべてが半数を超えている。
とくに「物流費」「人件費」は前年から大幅に増加しており、2024年問題 による運賃引き上げや人手不足の影響が顕著。
一方、「円安」を値上げ要因とする割合(12.4%)は前年より低下しており、外的要因から国内コスト要因中心のインフレへとシフトしている。
消費者行動の変化をどう読むか。“節約志向時代”の飲食店経営
長引く物価高と実質賃金のマイナスが続く中、消費者の財布のひもは確実に固くなっている。
家庭ではプライベートブランド(PB)商品や低価格スーパーへのシフトが進み、
「外食を控える」「注文品数を減らす」など、飲食行動そのものも慎重になっている。
この変化は飲食店にも直接影響を及ぼしており、
従来の価格設定やメニュー構成のままでは“選ばれにくい時代”が到来している。
その一方で、「ちょっと贅沢」「ご褒美外食」といった目的性・体験性の高い外食には一定の需要が残っており、
価格以上の満足感をどう演出できるかが、売上維持の鍵となる。
単純な値上げではなく、
-
・ボリューム・提供スピード・接客などで“価格に見合う価値”を明確にする
-
・少量メニューやセット構成を見直し、客単価を維持しながら満足度を高める
-
・サブスクリプションや会員特典などでリピートを促す
といった工夫が、節約志向下でも選ばれる店舗づくりに直結する。
価格をどう上げるかではなく、「どう納得してもらうか」が問われている。
今後の見通し:11月は小休止、年間2万1000品目前後に
2025年11月の値上げ予定は、9月末時点で 100品目未満 にとどまる見通し。
11カ月ぶりに前年同月を下回ることになりそうだ。
年内続いた“値上げラッシュ”はようやく小休止を迎える。
ただし、値上げ要因の中心が原材料高や人件費・物流費といった「内的コスト」に移っているため、
価格上昇圧力はすぐには解消されない。
年間では 2万1000品目前後 での着地が予想され、2022年以来3年連続で“高値上げ圧力”が続く公算が高い。
飲食業界に求められる「価格対応力」と「価値再構築」
飲食店にとって、この“値上げの連鎖”は原材料コストの直撃だけでなく、
メニュー設計や販売戦略の見直しを迫る大きな転換点でもある。
単なる価格転嫁ではなく、
-
自家製調味料・ソースによるコストコントロール
-
メニュー構成の再設計
-
原材料の代替利用(鶏肉・豆類など)
-
デジタルオーダー・セルフレジの導入による省人化
といった「構造的なコスト耐性づくり」が鍵となる。
値上げトレンドの先にある、“持続可能な外食経営”へ
2025年の食品値上げは、もはや一過性の現象ではない。
原材料・エネルギー・人件費といった内的要因が複合的に重なり、
「価格変動が常態化する時代」 に突入している。
外食産業にとっては、価格をどう抑えるかではなく、
「どんな価値を提供すれば価格を受け入れてもらえるか」 に焦点が移っている。
調達多様化、地産地消の推進、メニューの柔軟運用など、
変化を前提とした持続的な経営モデルの確立が急務だ。
2025年12月
2026年の値上げは大幅減速、それでも“安心できない”理由は?
帝国データバンクが2025年11月28日に公表した最新調査によると、2026年に予定されている飲食料品の値上げは1044品目にとどまり、前年同時点で公表されていた2025年見通し(4417品目)と比べて約8割減という大幅な減少ペースとなっている。2022年以降で見ても最も低い水準であり、来春にかけて続いていた断続的な「値上げラッシュ」は、一旦は収束局面に入る可能性が高いといえる。
一方で、この数字だけを見て「値上げは終わった」と判断するのは早計だ。
調査では、2026年の値上げ要因の99.7%が「原材料高」となっており、値上げの主因は人件費や物流費といったサービス要因から、再び「モノ由来」へと回帰している。
天候不順による不作や原材料価格の不安定さは今後も続く可能性があり、値上げ圧力が完全に消えたわけではない点には注意が必要だ。
酒類・飲料と加工食品に集中する値上げ、外食への影響は
2026年の値上げ予定品目を分野別に見ると、
最も多いのは「酒類・飲料」509品目、次いで「加工食品」397品目となり、この2分野だけで全体の約9割を占めている。
これは飲食店にとって、
・アルコール原価
・ドリンク原価
・冷凍食品・業務用加工食材
といった利益率に直結しやすい部分への影響が続くことを意味する。
一方、2025年に猛威を振るった調味料分野の値上げはピークアウトしつつあり、
「全面的な原価上昇」から「分野別・品目別の選別的値上げ」へとフェーズが変わり始めている点は、飲食店経営にとって重要な変化といえる。
消費者の“値上げ耐性”は限界に。価格戦略は次の段階へ
帝国データバンクの分析では、
・実質賃金の伸び悩み
・値上げ後の販売数量減少
・PB商品や廉価品へのシフト
といった動きが顕著になっており、消費者の価格拒否感はこれまで以上に鮮明になっている。
この状況下では、
「原価が上がったから値上げする」という単純な転嫁モデルは、ますます通用しにくくなる。
実際、2025年の平均値上げ率は15%と高水準でありながら、数量減少による売上鈍化に直面する企業も増えている。
飲食店経営者にとって今後重要になるのは、
値上げをする・しないの二択ではなく、どこで・どう吸収するかという判断だ。
飲食店経営者が2026年に向けて備えるべき視点とは?
今回の調査結果から見えてくるのは、
「値上げが落ち着く=経営環境が楽になる」ではないという現実である。
今後は、
・値上げが集中する酒類・飲料の粗利設計の見直し
・原材料価格が安定している食材へのシフト
・セット・コース構成による原価の平準化
・値上げせずに満足度を高める演出(量・体験・スピード)
・PB食材や業務用規格の再活用
といった、「価格を上げないための経営努力」そのものが競争力になる局面に入る。
値上げラッシュが一服する今こそ、
原価・価格・価値のバランスを再設計できる店舗が、次の局面で強さを発揮するだろう。
まとめ:値上げは“収束”ではなく“質が変わった”
2026年に向けて値上げ品目数は大きく減少する見通しだが、
原材料高を中心としたコスト圧力は依然として残っている。
これからの外食経営では、
「値上げにどう対応するか」から「価格変動を前提にどう設計するか」へ、
発想を切り替えられるかどうかが、生き残りを左右する分岐点となる。



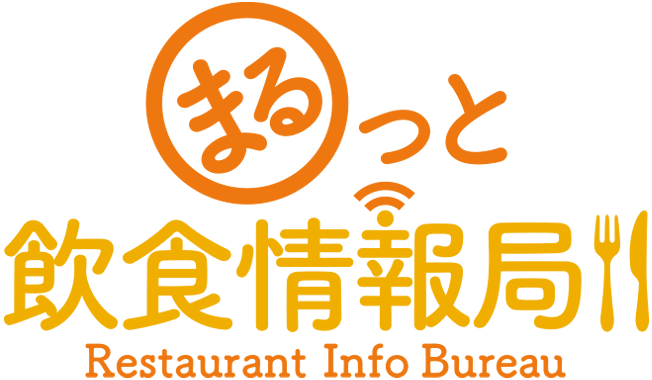




.png)
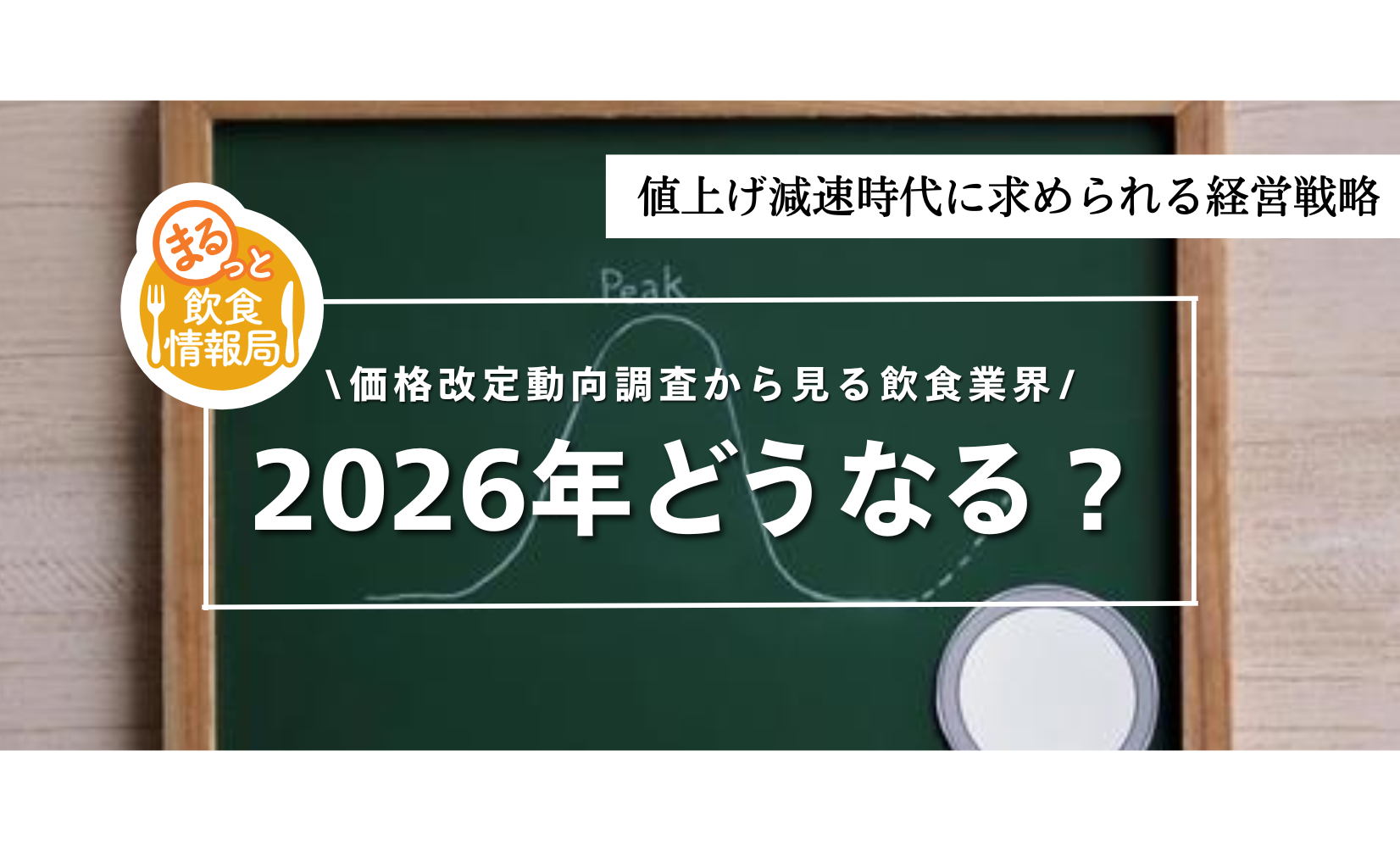
.png)
.png)
-1.png)
.png)

