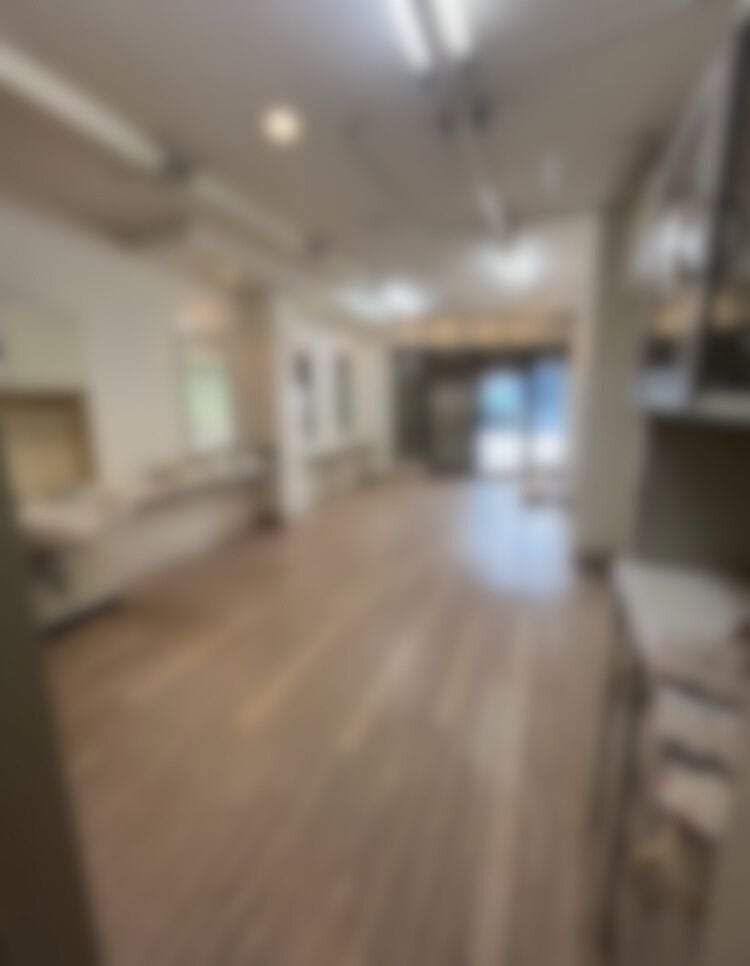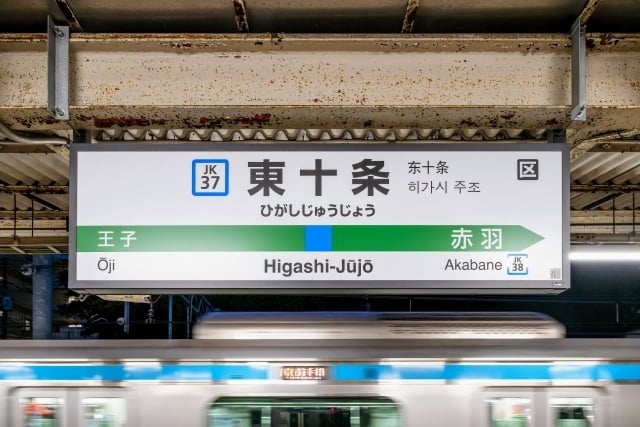【初心者向け】飲食店経営者が必ず知っておくべき!原価計算の簡単で効果的なやり方とは?

飲食店経営において、原価計算は避けて通れない課題です。メニュー価格の設定や仕入れの最適化、さらには利益率の向上など、原価計算は経営のあらゆる側面に影響を与えます。しかし、「原価計算なんて難しそう」「どこから手をつければいいかわからない」と、敬遠している方も多いのではないでしょうか。
この記事では、飲食店経営の初心者の方でも、簡単に始められる原価計算の方法を解説します。具体的な計算方法から、原価率の改善策、そして原価計算ツールのご紹介まで、幅広くご紹介します。ぜひ、この記事を参考に、貴店の原価管理を始めてみてください。
なぜ原価計算が大切なのか?
原価計算を行うことで、以下のメリットが期待できます。
メニュー価格の設定: 各メニューの原価を把握することで、適正な価格設定が可能になります。
仕入れの最適化: 不要な食材の仕入れを防ぎ、仕入れコストを削減できます。
利益率の向上: 原価率を下げることで、利益率を向上させることができます。
経営状況の把握: 経営状況を数値で把握することで、経営改善に繋げることができます。
原価計算の基本
原価計算の基本は、非常にシンプルです。
原価率 = (原価 ÷ 売上高)× 100
この式に、各メニューの原価と売上高を代入することで、原価率を計算することができます。
原価とは?
原価には、大きく分けて以下のものがあります。
食材費: メニューに使用される食材の購入費
人件費: 従業員の給与や社会保険料
経費: 水道光熱費、家賃、消耗品費など
原価率の目安
飲食店の原価率の目安は、業態やメニューによって異なりますが、一般的には30%~40%と言われています。
FLコストやFL比率を用いて計算することが多いです。
FLコストとは、飲食店の「Food(食材費)」と「Labor(人件費)」の合計金額を指します。具体的には、以下の要素で構成されます。
- Food(食材費): 食品や飲料の原価、材料費。
- Labor(人件費): 従業員の給与、賃金、社会保険料などのコスト。
FL比率は、飲食店の売上高に対するFLコストの割合を示す指標で、次の計算式で求められます。
FL比率(%) = (食材費 + 人件費) ÷ 売上高 × 100
業態ごとの原価率の目安が気になる方はこちらの特集もご覧ください!
原価計算の具体的なやり方
メニューリストの作成: すべてのメニューをリストアップします。
原価の算出: 各メニューに使用される食材の量と単価を把握し、原価を計算します。
売上高の算出: 各メニューの売上高を計算します。
原価率の計算: 上記の式に、原価と売上高を代入して原価率を計算します。
原価率を下げるための対策
食材の仕入れの見直し: より安い仕入先を探したり、大量購入による割引を交渉したりすることで、食材費を削減できます。
メニューの構成の見直し: 原価率の高い食材の使用量を減らしたり、別の食材に置き換えたりすることで、原価率を下げることができます。
ロス削減: 食材のロスを減らすことで、原価率を改善できます。
人件費の見直し: 人件費を占める割合が大きい場合は、人員配置の見直しや、時間帯別のシフト管理など、人件費削減策を検討しましょう。
原価計算ツールを活用しよう
原価計算は、手作業で行うと非常に手間がかかります。そこで、原価計算を効率的に行うために、専用のツールを活用することをおすすめします。
原価計算ツールには、以下の機能が備わっているものが多いです。
レシピ管理: メニューのレシピを登録し、自動的に原価計算を行うことができます。
食材の在庫管理: 食材の在庫状況を把握し、発注管理を効率化できます。
売上管理: 売上データを登録し、原価率を自動計算できます。
レポート作成: 原価率の推移や、メニュー別の利益率などをグラフや表で表示できます。
まとめ
原価計算は、飲食店経営において非常に重要な要素です。この記事で紹介した内容を参考に、ぜひ原価管理に取り組んでみてください。
弊社では、飲食店経営者の皆様が安定した利益を上げられるよう、物件探しのサポートをしております。FLR比率を意識した物件選びや、経営に最適な立地を見つけるためのコンサルティングを通じて、出店をサポートいたします。経験豊富なコンサルタントが、皆様の要望に合った物件探しを徹底サポートいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。