2019/09/07
ピンチを乗り越え掴んだヒント。時代の変化を追い続け、成長を重ねる

「ビストロバーパテ屋」や「肉酒場ブラチョーラ」等、肉業態を展開するハイライトインターナショナル株式会社(本社/東京都練馬区、代表/和田高明)。2011年5月に1店舗目となるAKITAKAを出店した後、2013年に法人化。現在は練馬や高円寺を中心に都内計7店舗を擁するフードサービス企業となった。しかしながら、これまで常に順調に成長してきたわけではない。むしろそれを糧にして今日の業容を築いてきた同社代表取締役の和田高明社長にこれまでの取組と今後の展望を伺った。
目次
畜産メーカーへ就職した後の飲食店経営、そのスタートダッシュとは
――現在、ビストロバー「パテ屋」をはじめとして、肉類をメインに扱う5業態7店舗を経営していますが、いつから飲食店経営者を志していたのですか。
学生時代からいつか起業したいと考えていました。でも当時は「飲食業界」と特定していたのでなく、漠然と「経営者を目指している」という程度でした。営業のような業務に苦手意識があったため、それを克服するという意味でまずは営業として就職しました。それで入社したのが畜産メーカーの米久株式会社です。
そこで、4年間営業を担当した後に、本社で仕入れや企画の業務を2年間担当させていただきました。本社異動後、2年間経験させていただいたら独立しようと決めており、米久で6年間勤務した後の2011年に1店舗目のAKITAKAを出店しました。その当時、米久で唐揚げ用鶏肉の企画を担当しており、唐揚げブームだったこともあって、唐揚げをメインに扱う業態で出店しました。
――そしてその1店舗目はすぐに軌道に乗ったのですね。
確かに、前職で学んできたことを活かすことによって月に100万円以上は利益が出ていました。ただ、それで調子にのってしまったことが災いしました。そして2店舗目はあまり考えず出店してしまったということもあり、大失敗となりました。そこで初めて「商売って大変なんだ」ということに気付きました。
そこが一番のピンチでしたね。2号店は開店から3カ月で閉め、約1000万円の損失となりました。さらに、当時「俺は偉いんだ」みたいな天狗状態になってしまった為、従業員のこともないがしろにしてしまい、2店舗目を閉店した段階で全員辞めてしまい、私と経験の浅いアルバイトしか残っていませんでした。
ハイライトインターナショナル株式会社代表取締役社長の和田高明氏
ピンチを乗り越えた秘策、「負けない店」「個人商店感」
――金銭面でも人材面でも大打撃を被ったようですね。そのピンチを乗り越え、その後の方向性等をどのように練り直していったのですか。
2店舗目を撤退した翌日に現在の「パテ屋高円寺店」の物件契約をしました。そこで「いかに負けない店にするか」ということにこだわり、店舗づくりを行いました。まず初期費用を出来るだけ抑えるために、物件取得費も安い居抜きの物件をほぼそのまま使用し、内装も自分たちで行いました。お金をかけられない分、店の営業で大切にしたのは「個人商店感」です。
――その「個人商店感」とはどのようなものですか。
その店にコミュニティがあることです。個店が生き残ることが出来るのは、そこにコミュニティがあり、いわゆる地域密着のような「個人商店感」があるからだと考えています。一番分かり易いのがスナックで、スナックに行って、通常の飲食店よりもかなり高い価格のボトルを入れるのは、そこにいる女将さんと、馴染みの常連客と話がしたいから、その空間代にお金を払っているのだと思います。したがって、このようなコミュニティのある店づくりを「個人商店感」と言っています。
従業員もお客様も含めて和気あいあいとした様子の「パテ屋高円寺店」
スタッフとの関係性を思いやりのある行動が変える
――一時は全社員を失う経験をしたということですが、現在従業員に対して特に大切にしていることはどのようなことですか。
思いやりです。離職するのも、仕事のパフォーマンスが向上しないのも、根本は人間関係から発生するものがほとんどと考えています。例えば、上司が部下に指導する際にも、相手なりの立場や想いを汲み取りながら指導しなさいと伝えています。
また、その逆も同じで、上司が思っていることの全ては部下には分からない、ということもしばしばあります。結局それぞれの行動に至った背景はその人にしか分からない。このような場合、同じことを言っていても、その背景が分からないでいても、本人なりに何か背景があるということを意識するだけで、自然と言い方は変わります。そうなることで、お互いに話を聞き入れやすくなり、より良い着地点が見つけやすくなります。
――従業員に対応する際に、これまでと言い方を変えたことで従業員が変化した、ということはありますか。
よくあります。例えば、最近では、社内イベント等みんなでわいわいするのがあまり得意ではない子に、自由参加であることをより明確に伝えたことがあります。元々自由参加ですが、みんな参加してくれることが多いため、自分だけ断りづらいというのがあるかなと思い、声をかけてみました。小さなことだったのですが、そうすることで、本人にとっては会社が多様性を認めている姿勢を感じてくれたようで、日々の業務でも、積極的に相談してくれるようになりました。小さなコミュニケーションも取りやすくなり、本人にとっても、周りにとってもより働きやすい環境になりました。
盛んに行われる社内イベントの一つであるBBQ
――従業員ごとに合わせて、対応も変化させているのですね。
そうですね。こうして日々、従業員ごとに細かく小さな配慮を積み重ねることで、従業員が会社を信用してくれます。そうすると、従業員は安心して働くことができることから、営業にも集中できるし、自ずと従業員もお客様へ個別に配慮しながら対応していくようになります。
喫煙者と禁煙者の距離を離すだとか、ファミリーのかたにはお子様が座りやすいベンチシートの席に案内するだとか、当たり前のことをやれていないお店は以外と多いと思います。来店の案内でも、お見送りでも、トーン、表情、行動も全く変わってきます。そういったことは、常日頃から従業員同士で思いやりを持って接していくと、自然とお客様へもこのような配慮をすることに気付いてきます。
より盛んなコミュニケーションを図る場にもなっている社内飲み会
「ハイライトインターナショナル」の今後の展開とは
――そのように試行錯誤を重ねながら変化し、成長する「ハイライトインターナショナル」の今後のビジョンを教えてください。
今は従業員たちに幸せになってもらいたいということが一番の思いです。独立したいと考えている従業員も多いので、できることならそのような人に今ある店舗を譲りたいと思っています。
一方、現実的には、一人でやっていくと心細く、誰かに頼りたいと思っている人も多い。そこで、相性が良い従業員をペアにして譲ることもパターンの一つとして考えています。僕は運営には携わらないものの、二人をサポートできればいいと思っているところです。今はまだ感覚的な段階ですが、このような形で社員独立の仕組みも整えようとしています。
――そのような仕組みづくりも含めて、今後が注目されます。今後の出店予定を教えてください。
今月東京・練馬に定食業態を出店する予定です。実はこの店舗は店としての運営だけでなく、試験的に他の役割ももたせようと考えています。
それは、従業員たちは夜中に営業が終了してから、面倒だということもあり、賄いを作らないで、帰りにラーメンや牛丼、コンビニ弁当ばかり食べている。このままだと体を壊すのではないかと思い、この店で健康的な弁当を作って従業員たちに配ろうかと考えています。当然、経営として成立をすることが前提としてありますが、両立することができれば、また一つ、当社の経営理念を体現することになると考えており、ワクワクしています。
――それでは最後にズバリ、現状に点数をつけるのであれば何点ですか。
んー、100点ですかね。自分で思い込めば100点じゃないですか。やっている時はこれが最高だと思ってやっています。そっちの方がバイタリティ湧きます。大変な時こそ、笑顔でポジティブな気持ちでみんなに声をかけて、支えていくことを心がけています。

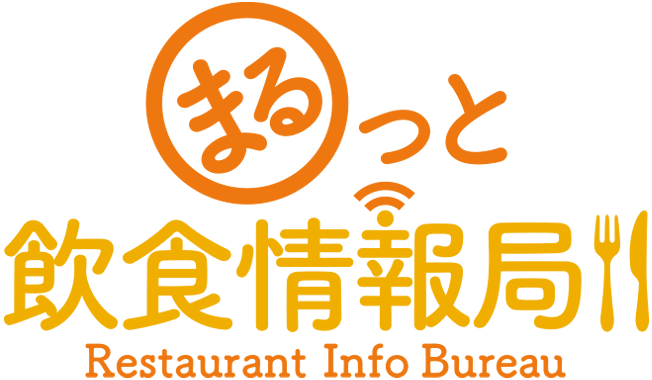







.png)
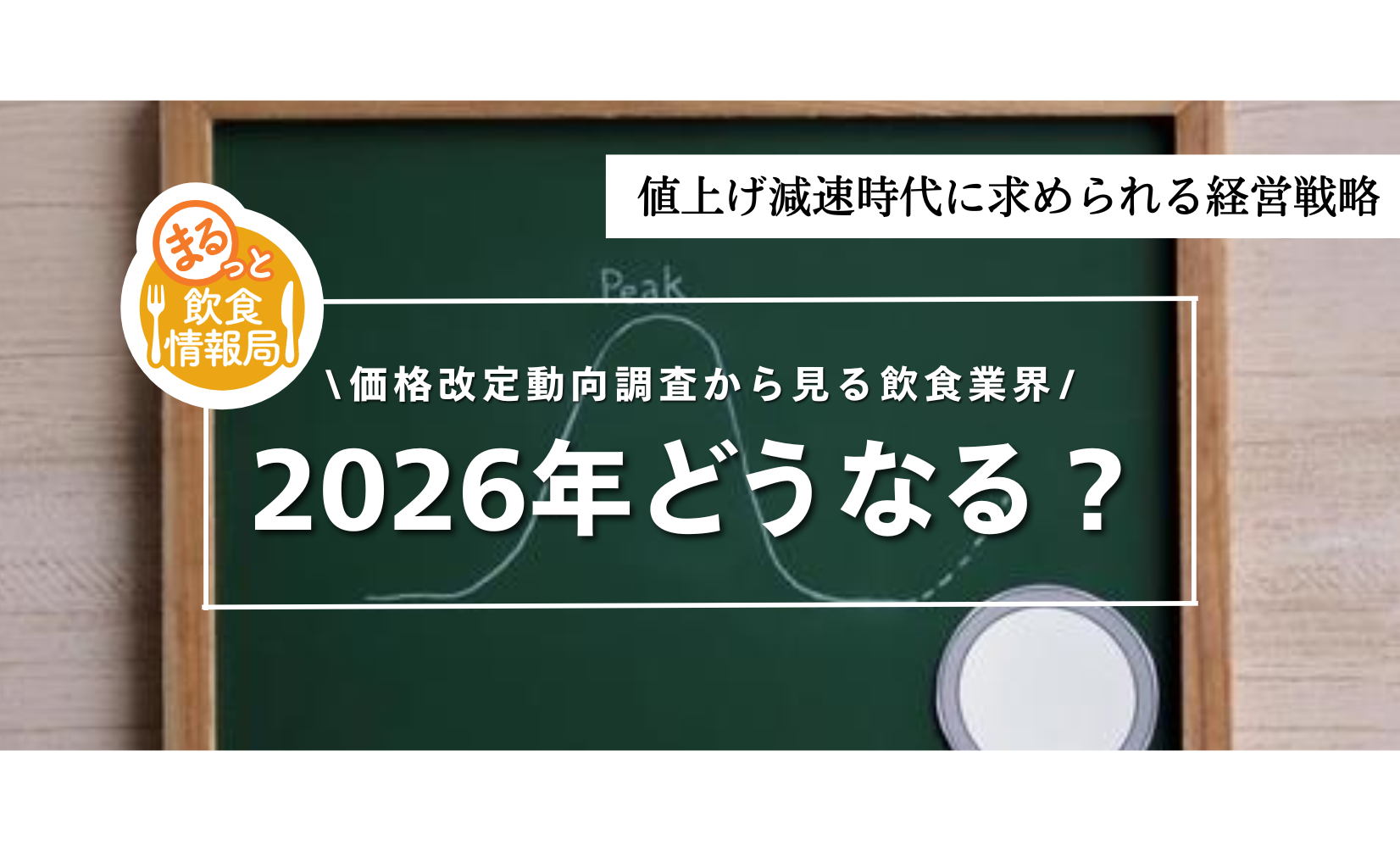
.png)
.png)
-1.png)
.png)

