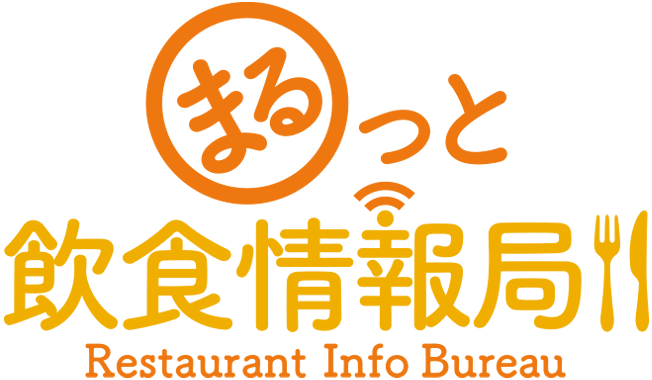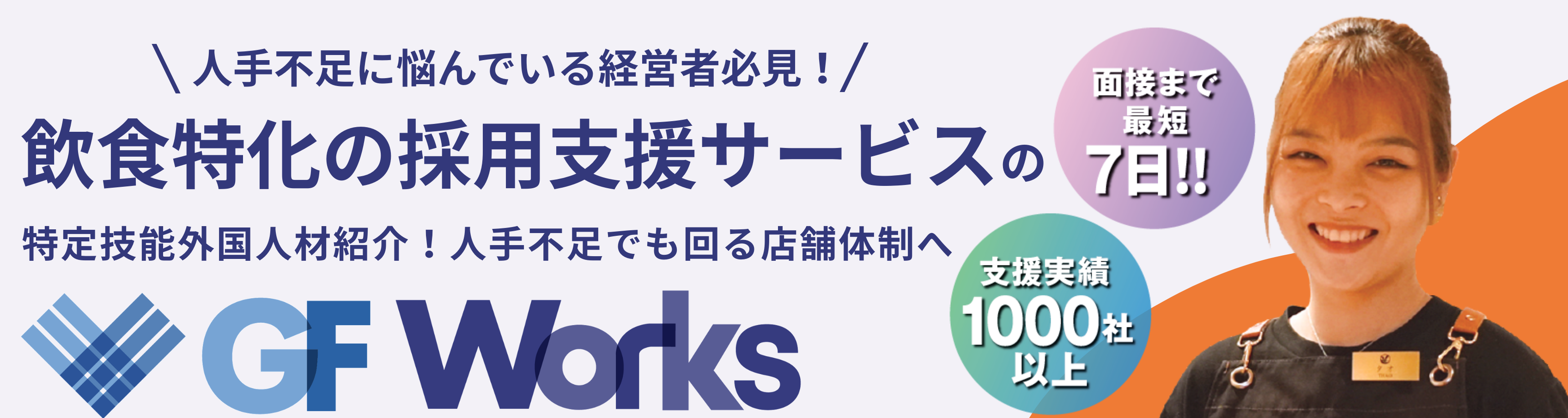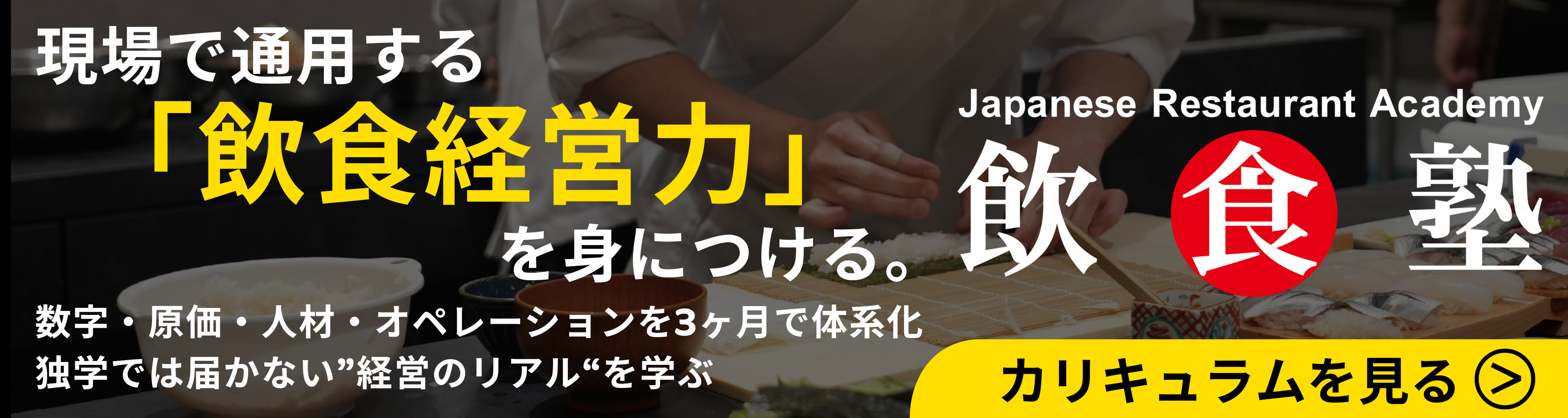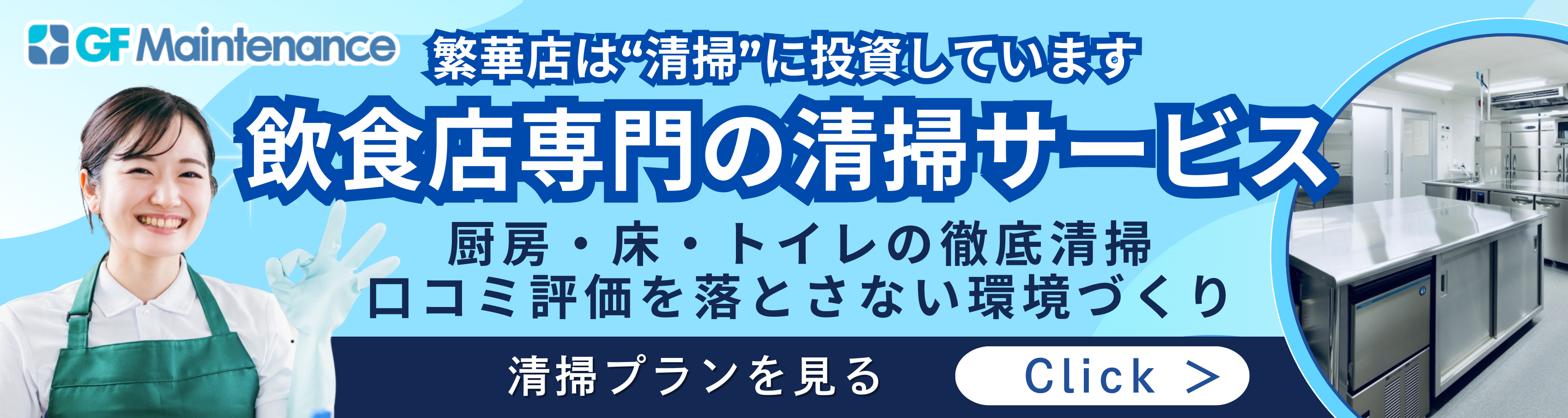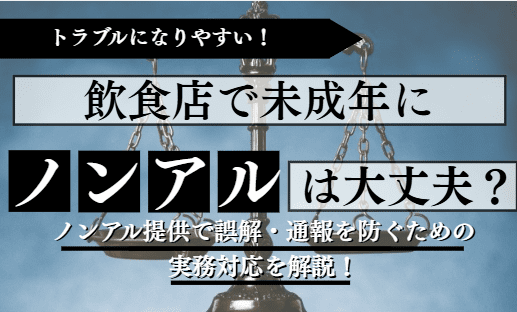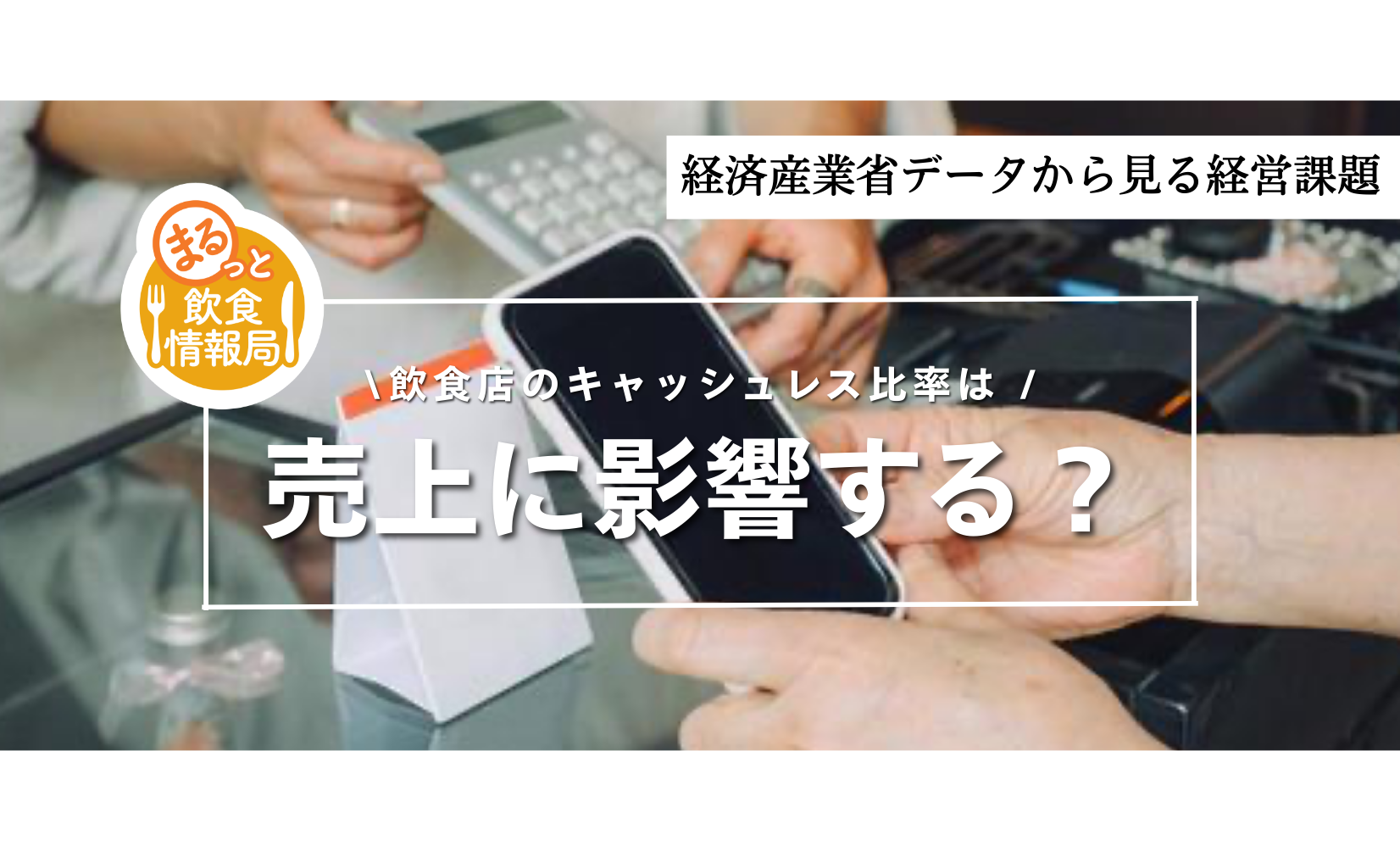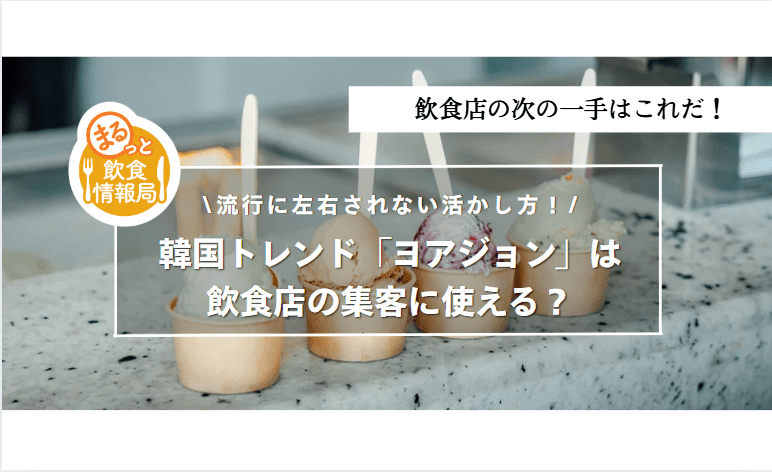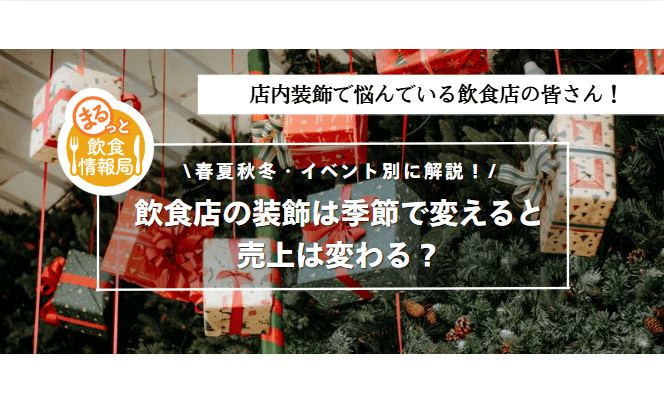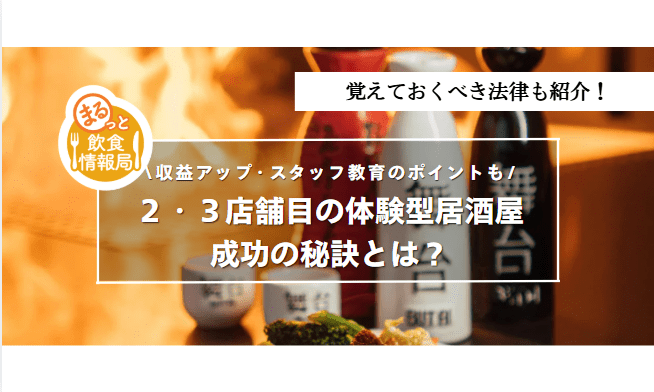2025/07/07
特定技能2号が外食業界を変える|試験結果初公表と2025年以降の人材定着戦略
-2.png?width=1000&name=%E9%A3%B2%E9%A3%9F%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%81%20(2)-2.png)
飲食業界にとって転機、特定技能2号の試験結果が発表
2025年6月、OTAFF(一般社団法人外国人食品産業技能評価機構)は「特定技能2号」に関する技能評価試験の合格者を発表した。今回注目を集めたのは、外食分野の結果が初めて公表された点である。すでに制度対象として追加されていた外食業界においても、ついに本格的な運用段階へと突入した形だ。
人材不足が深刻な飲食業界では、即戦力かつ長期雇用が可能な人材の確保が喫緊の課題となっており、特定技能2号の制度的活用に向けた準備を進めていた事業者も少なくない。試験合格者の発表により、今後は現場での実践的な受け入れが加速していくと見られる。
この制度により、従来は最大5年だった特定技能1号の就労期間が無期限となり、さらに家族の帯同も可能になるなど、外国人材の定着を大きく後押しする仕組みが整いつつある。今回の動きは、外食業界の労働環境改善と経営の安定化に向けた第一歩ともいえるだろう。
特定技能2号とは?外食分野での制度概要を再確認
「特定技能2号」は、外国人労働者の中でも、一定の業務経験と技術を有する熟練者に付与される在留資格である。2019年に導入された「特定技能制度」は、即戦力人材を対象とした就労ビザ制度であり、1号と2号に分類される。
特定技能1号は、主に単純労働の範疇とされる業務に対応し、最長5年間の在留が可能である。すでに外食業を含む12分野で運用されてきた。一方、特定技能2号は、より高い技術力・経験を有する労働者を対象としており、更新により事実上の永続的な滞在が可能。配偶者や子どもの帯同も許可されているのが大きな違いだ。
外食分野では2024年の制度改正により、正式に特定技能2号の対象業種に追加された。以降、各業態に応じた評価基準や試験内容の整備が進み、2025年には初の合格者が誕生することとなった。
2025年12月現在|特定技能2号は「人手不足対策」から「定着戦略」へ
2025年12月現在、外食分野における特定技能2号は「制度として整った段階」から「現場での活用が問われる段階」へと移行しつつあります。試験合格者の誕生をきっかけに、実際に2号への移行や長期雇用を見据えた人材育成・評価体制づくりに着手する飲食事業者も徐々に増えています。
一方で、特定技能2号は誰でも自動的に移行できる制度ではなく、一定の実務経験、日本語能力、現場を任せられるレベルの技能が求められるため、企業側には計画的な育成と受け入れ体制の整備が不可欠となっています。単なる人手不足対策ではなく、「将来の店長候補・現場責任者候補としてどう育てるか」という中長期視点で制度を捉える動きが広がりつつあります。
また、外国人材本人にとっても、在留期間の制限がなく家族帯同が可能となる特定技能2号は、日本での生活基盤を安定させる大きな転機となります。そのため、2025年現在は、制度の理解度や情報格差によって、企業ごとの対応力に差が出始めている状況ともいえるでしょう。
特定技能2号は、外食産業の人材不足を根本的に解決する「万能策」ではありませんが、適切に活用することで、慢性的な人手不足から脱却し、安定した店舗運営と人材定着を実現するための有力な選択肢となりつつあります。今後は、制度を「知っているか」ではなく、「どう使いこなすか」が、飲食店経営の明暗を分ける要素になっていくと考えられます。
飲食・外食業界における特定技能2号の活用ポイントとは?
特定技能2号がもたらす最大の利点は「定着率の向上」と「人材の戦力化」である。
外食業界では、これまで多くの外国人スタッフが特定技能1号や留学生アルバイトとして働いてきたが、在留期間の制限や生活不安から、長期的な戦力として定着しにくい状況があった。
今後は、厨房・接客いずれの業務においても、熟練スタッフをチームの中核に据え、教育・育成に時間をかけることが可能になる。また、家族帯同が認められることで生活の安定が図られ、離職リスクが大幅に低下する点も見逃せない。
とくに注目したいのが、2号取得に向けたキャリアステップの構築である。
すでに特定技能1号で働く外国人従業員に対して、スキルアップやリーダー教育の機会を提供し、段階的に2号取得を支援する仕組みを整備する企業が増えている。これにより、外国人材の定着と職場の生産性向上を同時に達成することが期待されている。
飲食店経営者が押さえるべき「特定技能2号」活用の現実的な判断軸とは?
飲食店経営者の立場で特定技能2号を考える際に重要なのは、「人手が足りないから採用する」という短期的視点ではなく、「誰を、どのポジションで、どれくらいの期間育てていくのか」という設計である。特定技能2号は、単なる現場要員の補充ではなく、将来的に店舗運営を支える中核人材を育成するための制度だ。そのため、採用時点で求める役割やキャリアイメージを曖昧にしたまま受け入れると、期待と実態のズレが生じやすい。2025年現在では、キッチンリーダー、シフト管理を担う現場責任者、複数店舗展開を見据えた育成枠など、具体的な役割を想定した上で特定技能2号を活用する企業ほど、定着率と生産性の両立に成功している。制度を「人手不足の穴埋め」として使うか、「将来への投資」として使うか――その判断が、今後の店舗経営に大きな差を生み出していくと言えるだろう。
まとめ:今こそ「特定技能2号」を軸とした人材戦略を構築する時
今回発表された「特定技能2号」外食分野の試験結果は、制度活用が現実のものとなったことを強く印象づけた。
人材確保の厳しさが増す中、飲食業界がこの制度をどう活かすかは、今後の経営の成否を分けるポイントになる。
外国人材を「補助要員」ではなく、「中核人材」として位置づけ、教育・評価・待遇制度を見直すことは、店舗運営の安定性やサービス品質の維持にも直結する。とくに今後は、制度の詳細理解だけでなく、実際の採用・マッチングに関する実務対応力も問われるようになるだろう。
「制度は理解したけれど、具体的にどう採用を進めればいいかわからない」と感じる経営者の方も多いのではないだろうか。そんな方に向けて、特定技能に対応した外国人材紹介サービスを活用するのもひとつの手段である。
今後、試験制度の拡充や評価基準の見直しが進むにつれ、採用競争も激化が予想される。自社の魅力を伝えられる採用体制をいち早く整備することが、優秀な人材を獲得するためのカギとなる。