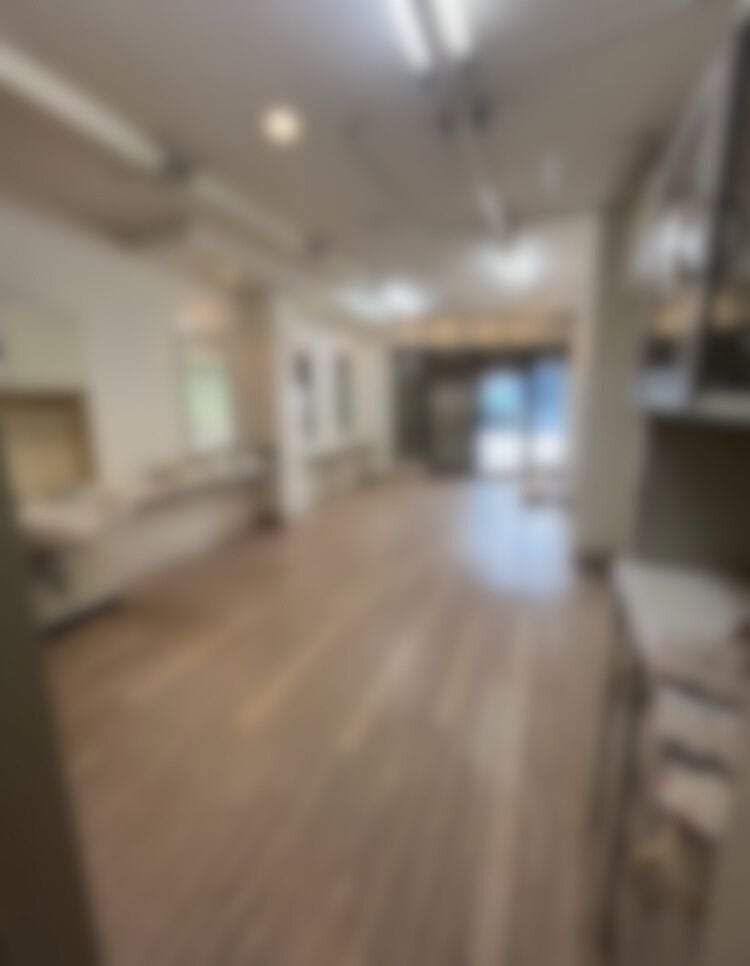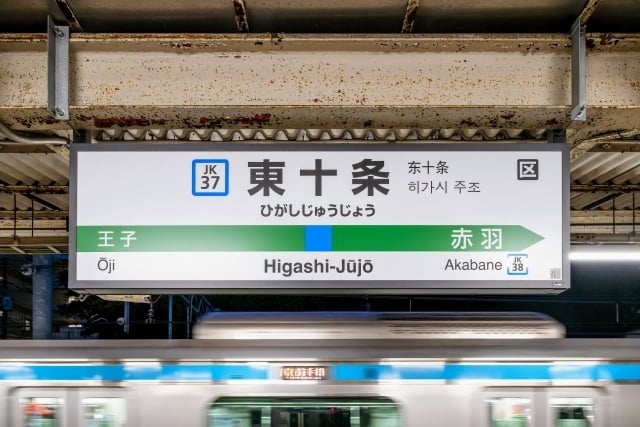飲食店でできるフードロス削減の取り組みと成功事例

誰もが一度は考えたことのある「もったいない」という気持ちが、実は地球規模の問題解決への第一歩になるかもしれません。日本国内で年間475万トンにも及ぶフードロス──これは、世界で飢餓に苦しむ人々を支援する食料量に匹敵します。私たちが無駄にしている食料が、どれだけの人々を救えるのか。食べ残しを持ち帰るだけで、外食産業もこの大きな変革に貢献できるかもしれません。そんな中、外食産業でも食品ロス削減に向けた取り組みが進みつつあります。その一つが「食べ残しの持ち帰り」です。欧米諸国では一般的な文化として根付いている一方で、日本では店側も消費者側もまだ広く受け入れられているとは言えません。今回は、日本国内での食品ロスの現状を整理するとともに、実際に食べ残しの持ち帰りを導入している事例をご紹介します。
令和4年度のフードロス量は475万トン|世界の食料支援量に匹敵
-1.png?width=484&height=300&name=napkin-selection%20(1)-1.png)
令和4年度に国内で発生したフードロスは、前年度比51万トン減の475万トンだったことが、農林水産省の推計で明らかになりました。これは、世界中で飢餓に苦しむ人々に向けた世界の食料支援量(2022年で年間480万トン)とほぼ同等に相当する量です。国民一人当たりに換算すると、毎日お茶碗約1杯分(約103g)の食べものが捨てられている計算になります。
フードロスは、本来食べられるにもかかわらず廃棄される食品を指します。その発生源は、食品関連事業者と家庭に分けられ、令和4年度はそれぞれ236万トンでした。事業系は前年度比43万トン、家庭系は同8万トン減少し、減少傾向が見られます。
内訳を見ると、事業系では、食品製造業が117万トンと最も多く、次いで外食産業が60万トン、食品小売業が49万トン、食品卸売業が10万トンとなっています。製造段階でのロスに加え、外食産業や小売店における売れ残りや廃棄も大きな課題となっていることがわかります。
近年、フードロス削減の機運が高まり、企業や消費者レベルでの取り組みが進んでいます。しかし、依然として膨大な量の食品が廃棄されている現状があります。政府は「食品ロス削減推進法」に基づき、2030年度までに食品ロスを半減させる目標を掲げています。
フードロスを減らすためには、事業者における需要予測の精度向上や、消費者における食品の適切な管理、食べきり意識の向上が求められます。私たち一人ひとりが「もったいない」という意識を持ち、食品を大切に扱うことが重要です。そして、飲食店では、食べ残しを持ち帰るための持ち帰りBOXの利用促進も、食品ロス削減に繋がる有効な手段と言えるでしょう。
食べ残しを持ち帰る… 妨げているのは「持ち帰り後の責任」への不安?

「外食時の食べ残しの持ち帰り」に関する見解
食べ残しを持ち帰る文化を広めたいと思いつつも、二の足を踏んでいませんか?お客様に「お持ち帰りBOX」を積極的におすすめしにくい要因として、持ち帰り後の食中毒など、万が一の際に飲食店側に責任が及ぶ可能性を懸念されているのではないでしょうか?
確かに、消費者庁・厚生労働省の見解では、持ち帰りは客側の責任としながらも、飲食店側が一切の責任を免れるとは言い切れないとしています。
① 持ち帰りに関する法規制
食品衛生法においては、客側・飲食店側ともに、外食時の食べ残しを持ち帰ることについて禁止する規定はない。
② 食べ残しを持ち帰った客が体調を崩した場合の飲食店の責任
・ 客側の責任で持ち帰った場合であっても、客が体調を崩した際に、飲食店側に一切責任が発生しないとまでは言い切れない。
・ (人の健康を損なうおそれがある食品の販売等を禁じる)食品衛生法第6条の問題が生じうる。
・ 医師の届出等により事案を探知した場合、自治体(保健所)の判断の下、必要に応じて疫学的な調査を行うなど、ケースバイケースで対応することとなる。
しかし、必要以上に不安に思う必要はありません。日頃から店内衛生管理を徹底し、持ち帰り時の購入した食品は速やかに食べるよう注意喚起を適切に行っていれば、過剰な心配は無用だと考えられます。
持ち帰りbox 利用の事例|食品ロス削減に取り組む飲食店
セブン&アイ・フードシステムズ、ロイヤルホールディングス、SRSHD、日本ホテルの4社は、環境省のモデル事業に採択され、2023年2月末まで持ち帰り促進活動を実施しました。これらの企業では、持ち帰り容器の有償化や宅配・テイクアウト容器としての活用も検討しており、今後さらに活動の幅が広がることが予想されます。
対象店舗-
- ・デニーズ
- ・ロイヤルホスト
- ・和食さと
- ・東京ステーションホテル
持ち帰りBOXの利用は、食品ロス削減に効果的なだけでなく、顧客満足度や企業イメージ向上にも繋がる取り組みです。多くの企業が導入を進める中、いち早く導入を検討してみてはいかがでしょうか?
持ち帰り推進事業の事例|長野県の例
長野県では、食品ロス削減に向けた「食べ残しを減らそう県民運動~e-プロジェクト~」が進行中です。このプロジェクトには、飲食店や宿泊施設、食品販売関連事業者が協力し、それぞれの店舗に合った取り組みを実施しています。令和6年3月1日時点で、長野地域振興局管内だけでも168店舗が登録され、地域全体で食品ロス削減を推進しています。
飲食店における具体的な取り組みのひとつが、「持ち帰り希望者への対応」です。これにより、料理の食べ残しを家庭で有効活用する動きが広がっています。
持ち帰り対応の具体例
- ・消費期限や保存方法を説明し、安全性を確保
- ・店内で持ち帰り可能であることを案内
- ・持ち帰り用の容器を設置し、気軽に利用できる環境を提供
さらに、食品衛生の注意事項もホームページで公開されており、消費者に対しては「自己責任の範囲で持ち帰りをお願いする」として、安心して利用できる仕組みを整えています。長野県の取り組みを参考に、あなたのお店でも食べ残しの持ち帰りを推進してみませんか?
(長野県地域振興局、「食べ残しを減らそう県民運動~e-プロジェクト~」)
持ち帰りの促進で、食品ロス問題に貢献!

日本の食品ロス量は年々減少しているものの、まだまだ大きな課題であることに変わりはありません。外食産業から発生する食品ロス量は全体の約2割を超え、主な要因である料理の食べ残しを減らす取り組みは急務となっています。食品ロス問題に貢献する1つのアクションとして、食べ残しの持ち帰りサービスの導入を検討されてみてはいかがでしょうか?