2024/12/20
ベジタリアンとビーガンの違いとは?|訪日観光客を囲い込むチャンス!飲食店が知っておきたい食の多様性について解説します!

近年、飲食業界では多様な食のスタイルが注目されています。その中でもベジタリアンやビーガンといった言葉は頻繁に耳にするようになりました。健康志向の高まりや環境問題への意識向上、訪日外国人観光客の増加もあり、飲食店にとっても無視できない存在になっています。特に外国人観光客は食文化や宗教、個人的な価値観からベジタリアンやビーガンであることが多く、彼らの食の選択肢に対応することは集客力の向上にもつながる重要なポイントです。
この記事では、"ベジタリアン"と"ビーガン"の違いを分かりやすく整理し、飲食店がどのように食の多様性に対応すべきかを詳しく解説します。これからの飲食店経営のヒントとして、ぜひお役立てください。
ベジタリアンとビーガンの違い

まずは「ベジタリアン」と「ビーガン」の違いについて説明します。同じように捉えられがちですが、実は大きな違いがあります。
ベジタリアンとは?
ベジタリアンとは、肉や魚介類を食べない人のことです。ただし、卵や乳製品といった動物由来の食材を摂取する場合が多く、完全に動物性食品を避けるわけではありません。ベジタリアンにはいくつかの種類があり、以下に代表的なものを紹介します。
-
ラクト・オボ・ベジタリアン:肉や魚は食べませんが、卵と乳製品は摂取します。
-
ラクト・ベジタリアン:肉や魚、卵は避けますが、乳製品は摂取します。
-
オボ・ベジタリアン:肉や魚、乳製品は避けますが、卵は摂取します。
ベジタリアンは、動物性食材を部分的に制限しながらも、比較的柔軟に食生活を維持している人が多いです。そのため、飲食店でも工夫次第で対応しやすい食事スタイルと言えるでしょう。
ビーガンとは?
一方でビーガンは、最も厳格なベジタリアンの一種です。肉や魚、卵、乳製品、ハチミツなどの動物由来の食材を一切摂取しない食生活を送ります。また、食事だけでなく、衣類や日用品、コスメなどライフスタイル全般においても動物性素材を避けることが一般的です。例えば、革製品やウール製品、動物実験を行っている化粧品を使用しないといった選択をする人が多いです。
ビーガンは単なる食事のスタイルではなく、動物愛護や環境保護、倫理的な価値観を大切にするライフスタイルとして広がっています。そのため、飲食店がビーガンメニューを提供する際は、動物性食材を完全に排除するだけでなく、調味料や出汁にも細心の注意を払う必要があります。
飲食店が知るべき、ベジタリアンとビーガンの需要

ベジタリアンやビーガン対応が求められる背景には、さまざまな理由があります。飲食店がその需要を正しく理解することで、新しい顧客層を取り込むチャンスが広がります。
観光客の期待に応える
海外ではベジタリアンやビーガンは一般的な食生活の一部です。特に欧米諸国では健康志向や環境問題への意識が高まっているため、ベジタリアンやビーガン人口が増加しています。彼らが訪日する際に「食べられるものがない」と感じることは珍しくなく、食文化の違いから和食であっても動物性の食材が多く使われていることが課題となっています。
例えば、和食に欠かせない出汁にはかつお節が使われることが多く、ビーガンやベジタリアンの観光客は敬遠してしまうことがあります。観光業と連携して集客を狙う飲食店にとっては、ベジタリアン・ビーガンメニューの提供は今後欠かせない取り組みとなるでしょう。
健康志向と環境保護への意識
ベジタリアンやビーガンは、健康志向や環境問題への関心から選ばれることも多いです。特に日本国内でも、動物性食品を減らし植物性食品を取り入れることで健康維持を目指す人が増えています。また、温室効果ガス排出量削減や動物福祉への貢献という観点から、ビーガンが注目されるようになりました。
飲食店にとっても、こうした健康や環境を意識するお客様に対応することで、ブランドイメージの向上や他店との差別化が図れる可能性があります。
食材の仕入れ先を工夫したい方は、農家から直接仕入れるというのも有効な方法です。
気になる方はこちらの記事も参考にしてみてください。
飲食店が取り入れやすい工夫

飲食店がベジタリアンやビーガンに対応するためには、以下のような工夫が効果的です。
ベジタリアン・ビーガンメニューの導入
定番メニューの一部をアレンジして、動物性食材を使わない料理を提供することから始めましょう。例えば、野菜たっぷりのカレーやパスタ、豆腐や大豆ミートを使ったハンバーグなどは、ベジタリアンやビーガン対応がしやすい料理です。和食であれば、味噌汁の出汁を昆布や椎茸に変えるだけで対応できます。
メニュー表への明確な表記
メニュー表には「V(ベジタリアン対応)」「VG(ビーガン対応)」といったマークを付け、対応している料理が一目で分かるようにしましょう。また、外国人観光客向けに英語での説明も加えることで、より親切な印象を与えることができます。
代替食材の活用
乳製品の代わりに豆乳やオートミルク、肉の代わりに大豆ミートやテンペなど、代替食材を活用することで料理の幅が広がります。
スタッフ教育の徹底
お客様からの質問に対応できるよう、ベジタリアンやビーガンに関する知識をスタッフ全員で共有することが大切です。調味料や出汁に動物性食材が使われていないか、確認できる体制を整えましょう。
SNSや口コミでの情報発信
ベジタリアンやビーガンメニューを提供していることをSNSで発信し、外国人観光客や健康志向のお客様に知ってもらう工夫も重要です。口コミサイトやSNSでの評価は、来店のきっかけになります。
食の多様性を取り入れて、集客力を高めよう
ベジタリアンやビーガン対応は、飲食店にとって特別なものではなく、新たな顧客層を取り込むための戦略の一つです。外国人観光客だけでなく、健康や環境に配慮する日本人のお客様にも喜ばれる取り組みです。
多様な食文化や価値観を尊重し、多くの人が安心して食事を楽しめるお店づくりを目指しましょう。飲食店がこうした柔軟な対応を行うことで、他店との差別化やブランド力向上につながり、長期的な成功への道が開けます。
店舗運営をさらに成功に導くために
弊社では、飲食店物件のご紹介サービスも行っております。お客様の希望条件や物件探しについて詳しくヒアリングを行い、専任の担当者が一緒に最適な物件を探します。また、店舗運営の成功に向けたご提案を行い、丁寧にサポートいたします。これから飲食店経営を始めたい方も、さらなる拡大を目指す方も、安心して次の一歩を踏み出せるよう全力でお手伝いいたします。ぜひご利用ください。


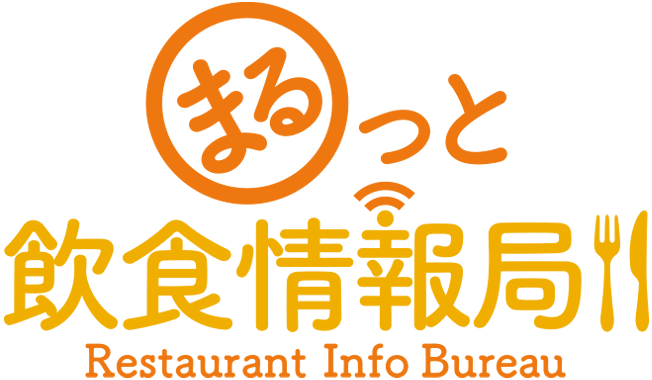

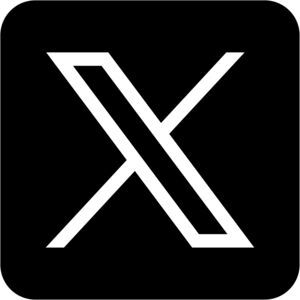



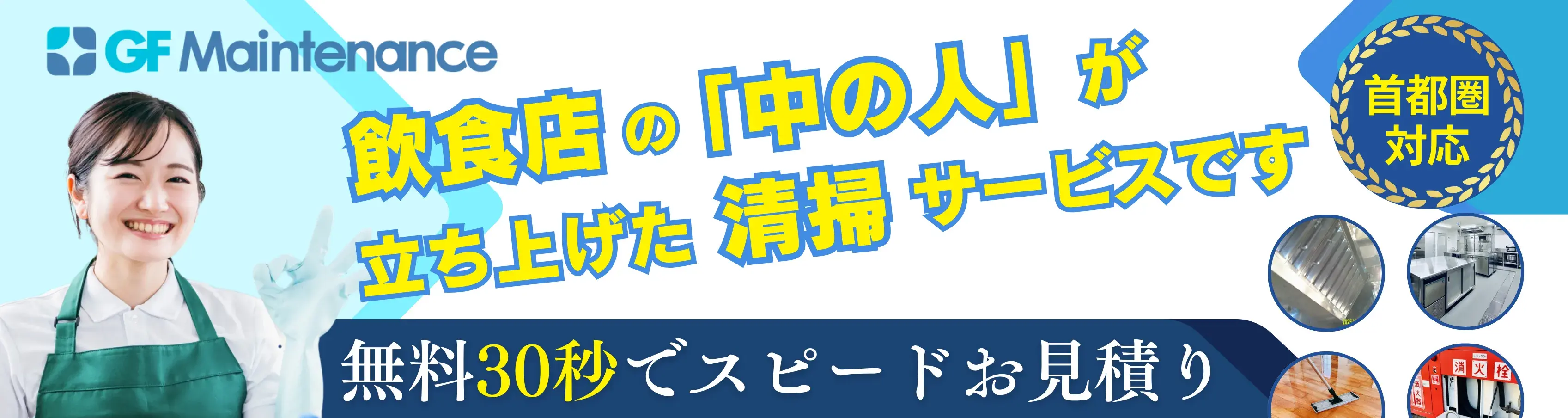
.png)
.png)
-1.png)
-1.png)
-1.png)

