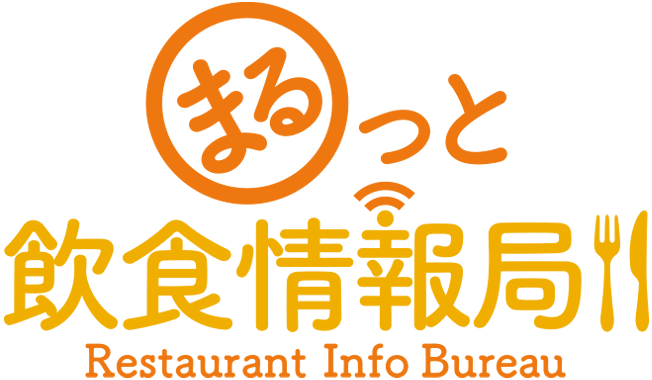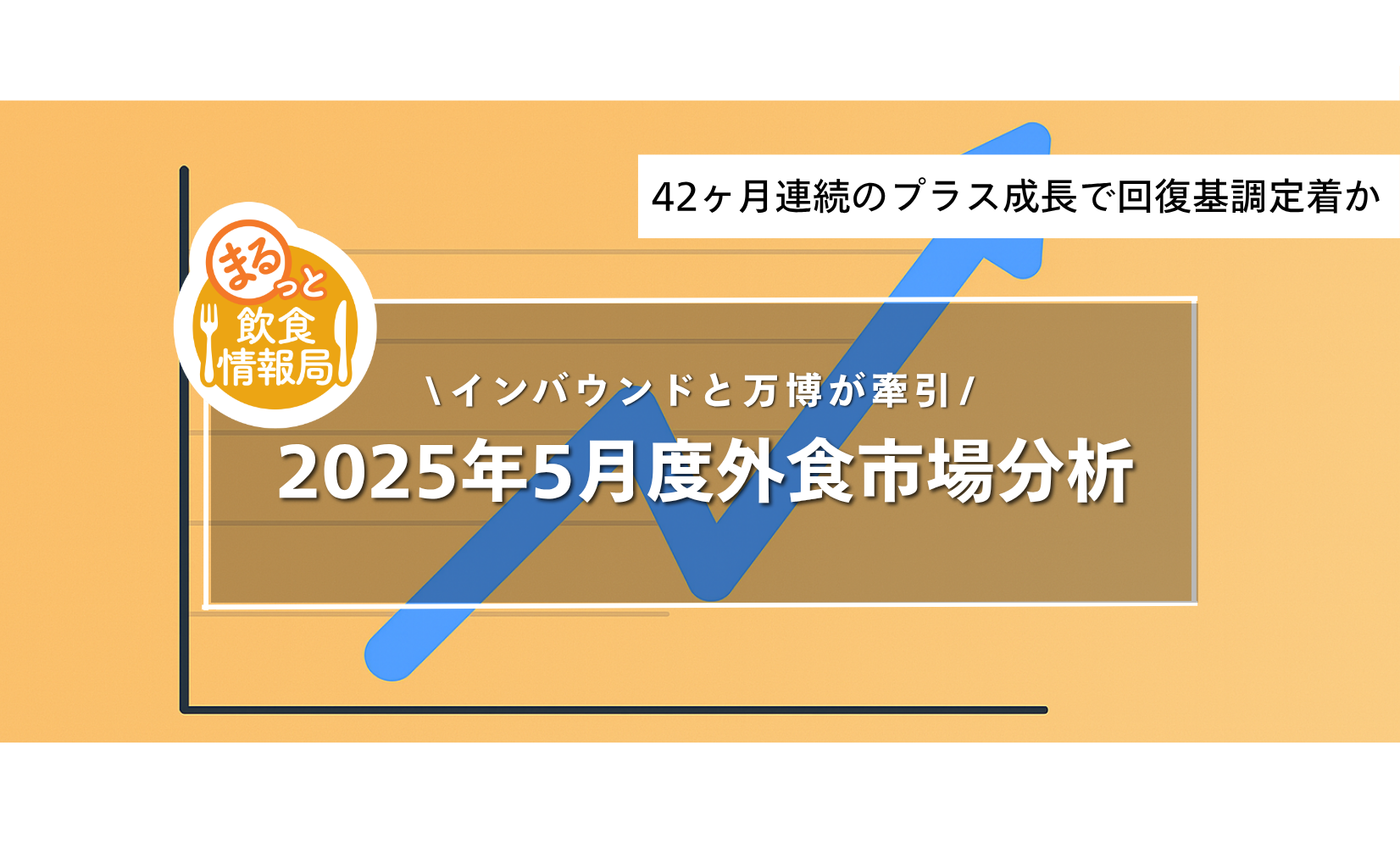- まるっと情報局|まるっと飲食情報局 G-FACTORY
- 「特定技能」とは?1号・2号との違いや雇用手順も解説|まるっと飲食情報局 G-FACTORY
2024/06/28
「特定技能」とは?1号・2号との違いや雇用手順も解説

日本の労働市場において、深刻な人手不足が多くの産業で課題となっています。その解決策の一つとして注目されているのが「特定技能」制度です。2019年に導入されたこの制度は、外国人労働者が特定の技能を持つことで日本での就労を可能にし、幅広い分野での活躍を支援しています。令和5年12月末時点で208,425人の特定技能外国人が日本に在留しています。(出典:出入国在留管理庁「入館最新特定技能在留外国人数の公表」の統計による)
本記事では、特定技能とは何か、対象となる業種、1号と2号の違いについて解説します。
特定技能とは?

特定技能とは、2019年に開始された日本の在留資格のことです。人手不足は年々深刻化し、日本の経済・社会基盤の持続可能性を脅かす可能性があると推測されています。そこで、人材確保が難しい状況にある産業分野において、一定の専門知識や技能を持つ外国人を受け入れるための制度です。
特定技能の1号と2号は何が違う?

特定技能には、「1号」と「2号」の2種類の在留資格があります。
簡潔に説明すると、「特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格であり、「特定技能2号」は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。(引用:出入国在留管理庁)
|
1号 |
2号 |
|
|
在留期間 |
1年(上限5年まで) 6か月又は4か月ごとの更新が必要 |
3年 1年又は6か月ごとの更新が必要 |
|
技能水準 |
試験等で確認 |
試験等で確認 |
|
日本語能力水準 |
生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 |
試験等での確認は不要 |
|
家族の帯同 |
基本的に認めない |
要件を満たせば可 |
|
受け入れ機関又は登録支援機関による支援 |
あり |
なし |
在留期間の上限
特定技能1号が上限5年、特定技能2号の場合は更新する限り上限なく在留できます。つまり、更新を忘れなければ実質永住できるということです。永住といっても、特定技能は就労ビザの一種なので「雇用されていること」が前提となります。
永住権の要件を満たせる可能性
特定技能2号のみ、在留期間の更新に上限がありません。特定技能の資格を取得してから10年を超えると「永住権の申請」が可能になります!
求められる技能水準
職場で求められる技能レベルは、1号よりも2号の方が上です。
特定技能1号は指示を受けながら作業に従事するのに対し、特定技能2号は他者を指導・管理することが求められます。
日本語能力水準
特定技能1号の場合、技能試験に加えて日本語能力も確認されます。国内外で定期的に実施されています。
支援の必要性
特定技能1号では、外国人支援は必須です。直近2年間で外国人の受入れがなく、外国人社員が在籍していない場合は「登録支援機関」へ支援を委託しなければなりません。
この理由として、「特定技能外国人を初めて受け入れる企業がすべての支援を自力で行うのが難しいため」と「支援にかかる企業側の手間を減らすため」が挙げられます。
一方、特定技能2号では、外国人支援は不要です。
家族の帯同の可否
特定技能1号は認められていませんが、特定技能2号は、要件を満たせば配偶者や子の帯同が認められます。この場合、配偶者や子には在留資格が与えられ、日本で生活することが認められます。
特定技能の12分野(旧14分野)とは?

特定技能外国人を受け入れる特定産業分野は、1号に12業種(旧14業種)、2号に11業種あります。
<1号の場合>
・介護
・ビルクリーニング
・素形材、産業機械、電気電子情報関連製造業(2022年に統合)
・建設
・造船、船用工業
・自動車整備
・航空
・宿泊
・農業
・漁業
・飲食料品製造業
・外食業
※2022年4月の閣議決定及び同年5月の関係省令施行により、「素形材産業」「産業機械製造業」「電気・電子情報関連産業」の3分野が統合され、「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」に一本化されました。
<2号の場合>
・ビルクリーニング
・素形材、産業機械、電気電子情報関連製造業(2022年に統合)
・建設
・造船、船用工業
・自動車整備
・航空
・宿泊
・農業
・漁業
・飲食料品製造業
・外食業
特定技能と技能実習の違いは?
「特定技能」と「技能実習」の違いは以下の通りです。大きな違いは職種と在留期間です。
技能実習の方が職種が自由に選べるため、外国人にとって日本で働くハードルが低いと言えます。2つの制度の違いを詳しく見ていきましょう。
|
技能実習 |
特定技能 |
|
|
目的 |
経済発展の援助 |
人手不足の解消 |
|
職種 |
制限なし |
14業種 |
|
対象国 |
15か国 |
9か国 |
|
在留期間 |
技能実習1号:1年以内 技能実習2号:2年以内 技能実習3号:2年以内 |
特定技能1号:5年以内 特定技能2号:制限なし |
|
試験 |
なし (介護はN4相当の日本語力が求められる) |
技能水準や日本語能力水準を試験で確認 |
|
家族帯同 |
不可 |
2号のみ可 |
|
転職可否 |
原則不可 |
同じ職種のみ可 |
資格の目的
技能実習と特定技能は“目的”が大きく異なります。
<技能実習>
日本の技術を開発途上国の人に伝えて経済発展を図る
<特定技能>
日本国内の労働力不足を解消する
技能実習は、現地での技術習得が難しい状況を鑑みて20年以上前から実施されています。
働ける業種
先程、特定技能の14業種について解説しましたが、技能実習の場合は職種が無制限です。
ただし、技能実習2号から3号へ移行する場合、移れる職種は制限がかかります。
対象国の数
法務省による送り出し国の数は、技能実習の方が少し多いです。
<技能実習>
・インド
・インドネシア
・ウズベキスタン
・カンボジア
・スリランカ
・タイ
・中国
・ネパール
・バングラデッシュ
・フィリピン
・ベトナム
・ペルー
・ミャンマー
・モンゴル
・ラオス
<特定技能>
・ベトナム
・フィリピン
・カンボジア
・中国
・インドネシア
・タイ
・ミャンマー
・ネパール
・モンゴル
在留期間
技能実習と比べて、特定技能は日本で働いてもらうのが目的なので在留期間は長めです。中でも特定技能2号は在留期間に上限がないため、永住権を得られる可能性があります。
試験の有無
技能実習と特定技能では、入国時の試験が異なります。
<技能実習>
原則、試験制度なし
(介護食の場合は、N4レベルの日本語能力が求められる)
<特定技能>
・全分野共通の日本語試験(国際交流基金日本語基礎テスト)
・分野別の技能試験(介護職は追加で別途日本語試験が必要)
家族帯同の可否
技能実習は数年働いて母国に帰ることが決まっているため、家族は呼べません。しかし、特定技能2号は在留期間に制限がないため、家族を呼ぶことができます。
ただし、家族とは配偶者・子を指し、親や兄弟姉妹は該当しません。
特定技能外国人を雇用するには?
「では実際に雇用したいときはどこに相談すればいいの?」と思う方もいるでしょう。
特定技能外国人の雇用を考えている人は、まずは最寄りの“地方出入国在留管理局”に相談してみましょう。インターネットで検索してみてください。
受入れ機関と登録支援機関
特定技能外国人を雇用する上で密接に関わるのが「受入れ機関」と「登録支援機関」です。この2つの機関の役割は何なのか解説します。
<受入れ機関>
「特定技能所属機関」とも呼ばれています。特定技能外国人を実際に受け入れ、支援する起業・個人事業主のことです。受入れ機関は、働きたいと所望する特定技能外国人と“特定技能雇用契約”を結びます。この契約では、外国人の給料が日本人と同等であることなどの所要の基準を満たしていることが求められます。
受入れ機関の義務は以下の4つです。
①外国人と結ぶ雇用契約が適切であること(例:給料を適切に支払う)
②受入れ機関自体が適切であること(例:労働法令違反の有無)
③外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援する)
④外国人を支援する計画が適切であること
<登録支援機関>
登録支援機関とは、受入れ機関から委託を受け、1号特定技能外国人支援計画の全ての業務を実施します。受入れ機関は、特定技能1号外国人に対して支援をおこなわなければいけませんが、その支援のすべてを「登録支援機関」に委託することができます。
登録支援機関としての登録を受けるためには、「当該支援機関自体が適切であること」と「外国人を支援する体制があること」が基準になります。
登録支援機関の義務は以下の2つです。
①外国人への支援を適切に実施すること
②出入国在留管理庁への各種届出をおこなうこと
特定技能外国人とマッチする方法
特定技能制度では、監理団体や送出機関は設けていません。受入れ機関が自主的に採用活動をおこなうか、ハローワーク等を通して募集をするのが一般的な方法です。
受け入れる人数については、介護および建設分野を除いて上限はありません。
雇用する際の注意点
特定技能外国人を雇用する際は省令等で定められたいくつかのルールを遵守する必要があります。代表的な義務が、雇用した特定技能1号の外国人に対する生活支援です。雇用した後は、「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、その義務を確実に履行しなければいけません。
また、「各種届出を随時または定期におこなうこと」「特定産業分野ごとに分野所管省庁が設置する協議会の構成員になること」等が求められます。
疑問点や不明点がある場合は、最寄りの地方出入国在留管理局に相談することができます◎
特定技能を取得するには?
特定技能試験は、日本での就労を希望する外国人にとって重要なステップです。
在留資格「特定技能」を取得するには、一般的に「日本語能力」と「取得分野の技能」に関する2つの試験に合格する必要があります。
日本語能力試験で求められるのは“N4レベル”(日常的な会話ができる)の日本語能力です。
特定技能の取得方法は、1号と2号で異なりますので注意が必要です。
特定技能1号の取得方法
在留資格「特定技能1号」を取得する方法は以下の2パターンに分けられます。
①特定技能測定試験に合格する
②技能実習から移行する
特定技能測定試験は、日本語能力と職種ごとの技能を確認する2つの試験をクリアしなければなりません。
技能実習から特定技能1号へ移行する場合、取得までの流れが変わります。
技能実習と特定技能の職種に関連性がある場合は、日本語試験&技能試験が免除されます。関連性がない場合でも、日本語試験は免除されます。ただし「良好に技能実習2号を修了していること」が条件なので注意が必要です。
特定技能2号の取得方法
在留資格「特定技能2号」を取得するには、以下の条件を満たす必要があります。
①特定技能2号評価試験または技能検定1級に合格する
②監督・指導者として一定の実務経験を積む
特定技能1号から移行するケースが一般的です。ただし、特定技能1号を取得していなくても、高い技能を持っていることが認められれば2号を取得することは可能です。
日本語能力に関する試験は、特定技能2号の場合は実施不要です。
外国人の雇用を考えているならGF WORKSへ!
GF WORKSは、登録支援機関であるG-FACTORYが運営する外国人材の採用から入社までを一気通貫でサポートするサービスです。
詳細は公式HPよりご確認ください!
GF WORKSの特徴
飲食に特化した人材紹介
「外食業で働くこと」を目的としたビザを取得できる人材ですので、日本の飲食業界で働くことを心に決めています。特定技能ビザ取得要件を満たす日本在住外国人材のみのご紹介です。いずれも「日本語能力試験」および外食業・飲食料品製造業分野の「特定技能試験」に合格した方です。
初めての外国人採用でも安心のサポート
直営店も運営する当社では、特定技能外国人材の採用実績が多数。外国人採用が初めての企業様・オーナー様に安心してもらうべく、G-FACTORYが採用決定まで完全サポートいたします。
初期費用がタダ!成功型報酬採用
入社まで費用はかかりません。「求人にかかる費用を抑えたい」「広告コストをかけても人材が集まらなかった」というお悩みを抱える飲食店様は多数です。
入社後もワンストップでサポート!
定期面談や書類提出などの煩雑な必須業務を当社がサポートいたします。
お問い合わせから人材紹介まで最短3日以内も可能!
サービスのご案内および募集条件の確認で概ね1時間以内に完了。
ウェブ上でのご契約いただき、最短当日中の募集開始、3日以内に人材のご紹介を開始することも可能です。
何度も打ち合わせを行ったり面接調整の電話で手を取られることも少ないため、お忙しいご担当者様でも安心してご利用開始可能です。
まとめ
特定技能制度は、日本の労働力不足や経済成長に寄与する重要な制度です。今後も外国人労働者の受け入れを円滑に進めるために、制度の運用方法や改善点について検討が行われるでしょう。私たち日本人も、日本で働く外国人をもっと受け入れ、彼らが日本を支える重要な人材であると認識するべきです。