2025/04/18
36協定の特別条項とは?書き方と申請方法を6STEPでわかりやすく解説
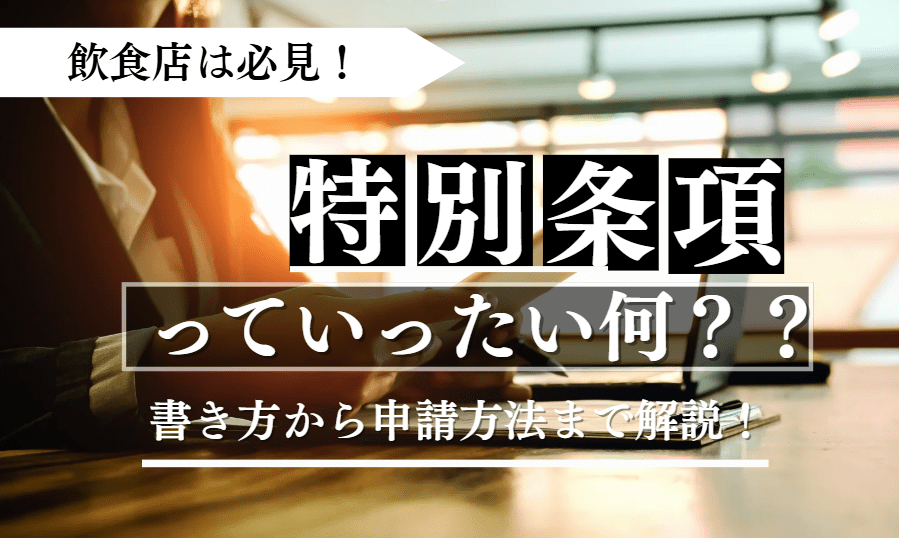
従業員を雇う経営者の方で、以下のようなお悩みはありませんか?
「特別条項の具体的な内容や上限規制がよくわからない」
「特別条項付き36協定の正しい書き方や申請方法を知りたい」
「特別条項に関する法的リスクを理解し、適切に対応したい」
本記事では、36協定の特別条項の基本概念から、上限規制、書き方と申請方法の6STEPなど詳しく解説します。
外食分野においては特別条項付36協定を締結する場合が通例となっていますが、特別条項付き36協定の適用条件や手続きが厳格化され、正しい理解と対応が求められています。
36協定は労働基準法に関連した企業と労働者が締結する協定であることから、国籍を問わず日本で働く労働者には原則適用されることになるため自社の人材不足解消のために外国人人材の雇用を検討されている企業も知っておかなければならない情報です。
労働基準法違反のリスクを避け、従業員の健康と安全を守るためにも、ぜひ本記事を参考に、適切な36協定の運用を目指してみてください。
なお、弊社G-FACTORY株式会社では、飲食業界の人材不足を解消するため外国人人材の採用支援から就労者の在留資格・特定技能ビザ取得支援、企業側の受入支援まで外国人人材の採用サポートを一気通貫で行っています。
自社の飲食店で、外国人材による人材不足の解消を図りたい企業様は、以下のページからお気軽にご連絡ください。
36協定の特別条項とは?

36協定の特別条項とは、特別の事情がある場合に限り、36協定で定められた時間外労働の上限(月45時間・年360時間)を超えての労働が可能な取り決めです。
特別条項が必要な理由は以下のとおりです。
-
-
• 予見が不可能な大幅の業務量増加に対応するため
-
-
• 緊急時や繁忙期の一時的な労働時間延長を合法的に行うため
-
• 企業の業務継続性を確保しつつ、労働者の健康と福祉を守るバランスを取るため
また、以下のような特別条項が適用される具体的な事例があります。
-
• 突発的な仕様変更への対応
-
• 製品不具合の緊急対応
-
• 大規模なクレーム対応
-
• 臨時的な受注の集中
-
• 突発的な納期変更
-
• 年末の決算業務
- • システムエラーの緊急対応
時間外労働の上限規制に関して、詳しくは以下のリンクをご参照ください。
なお、特別条項は、予見できない業務量の増加や緊急事態に対応するための仕組みですが、適用は慎重に判断してください。
なぜなら、安易な特別条項の適用は、長時間労働や過重労働につながるリスクがあるためです。
36協定の特別条項って、上限規制があるの?

実はそうではありません。36協定の特別条項を結んだからといって、無制限に残業をさせられるわけではありません。2019年の働き方改革関連法によって、時間外労働には明確な上限が設けられています。
具体的な上限規制は次のとおりです。
-
• 年間の時間外労働は720時間以内
-
• 2〜6ヵ月平均の時間外労働と休日労働は80時間以内
-
• 月の時間外労働と休日労働の合計は100時間未満
-
• 月45時間を超える時間外労働は年6回まで
これらの規制は、長時間労働による健康被害を防ぎ、労働者のワークライフバランスを守るために設けられました。
2019年4月の働き方改革関連法施行により、特別条項にも明確な上限が設定され、過度な長時間労働を抑制する仕組みが整えられたのです。
また、特別条項の適用は、あくまで臨時的・一時的な対応のためのものです。
恒常的な長時間労働は労働者の健康を損なうリスクがあるため、特別条項の適用は慎重に判断しましょう。
なお、時間外労働の上限規制に関して、詳しくは以下のリンクをご参照ください。
特別条項付き36協定って、新様式では何が変わったの?

結論から言うと、新様式ではこれまで以上に詳細な記載が求められるようになりました。
その背景には、2019年の働き方改革関連法による労働基準法の改正があります。時間外労働の上限規制が明確になり、特別条項の適用条件や手続きも厳格化されたためです。
新様式「様式第9号の2」では、以下のような項目を具体的に記載する必要があります。
-
• 臨時的に限度時間を超えて労働させることができる場合
(例:突発的な仕様変更、製品トラブル、大規模なクレームへの対応)
-
• 限度時間を超える時間外労働の上限
-
• 限度時間を超える労働に係る割増賃金率
-
(25%を超える率を努力義務に設定)
-
• 限度時間を超える労働に係る健康確保措置
つまり、「とりあえず協定書を作ればいい」ではなく、具体的な事由や対策を明記することが必須になったのです。
新様式に沿った記載と運用を徹底することは、特別条項付き36協定を適正に活用するために欠かせません。従業員の健康と安全を守るためにも、最新の様式に基づいて準備しましょう。
特別条項付き36協定って、どう書けばいいの?【記載例つき2STEP】

特別条項付き36協定の書き方は、以下の2STEPで行います。
-
• 様式の入手
-
• 必要事項の記入
それぞれのSTEPを詳しく解説します。
①様式の入手
特別条項付き36協定の様式は、厚生労働省のWebサイトからダウンロードするか、労働基準監督署の窓口で入手ができます。
特別条項付き36協定には専用の様式(様式第9号の2)が定められており、正確な記入と適切な提出が、法令遵守のために必要です。
厚生労働省の「主要様式ダウンロードコーナー」から「時間外労働・休日労働に関する協定届(特別条項)様式第9号の2」をダウンロードできます。
また、最寄りの労働基準監督署の窓口で直接受け取るのも可能です。予約は不要ですが、窓口の対応時間に注意してください。
なお、特別条項付き36協定の適正な運用には、正しい様式の使用が不可欠です。必ず最新の様式を入手するようにしましょう。
②必要事項の記入
「様式第9号の2」を使用し、上限時間、臨時的な特別の事情、健康確保措置などの必要事項を詳細に記入しなければなりません。
具体的には以下の項目を記入します。
-
• 臨時的に限度時間を超えて労働させる具体的事由
(例:突発的な仕様変更、製品トラブル、大規模なクレームへの対応)
-
• 限度時間を超える時間外労働の上限
-
• 限度時間を超える労働に係る割増賃金率
(25%を超える率を努力義務として設定)
-
• 限度時間を超える労働に係る健康確保措置
(例:医師による面接指導、深夜業の回数制限)
-
• 労働者代表および上限時間確認のチェックボックスにチェックを入れる
なお、「限度時間を超える時間外労働の上限」で記入する内容は以下のとおりです。
-
• 月100時間未満(休日労働含む)
-
• 年間720時間以内
-
• 限度時間を超える回数は年6回以内
-
• 複数月平均80時間以内
特別条項付き36協定の記入は、法令遵守と従業員の健康確保のために重要な手続きです。記入漏れや誤記入がないよう、十分に確認しながら進めるようにしていきましょう。
特別条項付き36協定って、どう書けばいいの?【記載例つき4STEP】

特別条項付き36協定の申請方法は、以下の4STEPで行います。
-
• 労使間での協定締結
-
• 就業規則の変更
-
• 労働者への周知
-
• 労働基準監督署への届出
それぞれのSTEPを詳しく解説します。
①労使間での協定締結
特別条項付き36協定の内容が、就業規則の絶対的必要記載事項である労働時間や休日、または割増賃金等に関する事項に影響を与える場合は、就業規則の変更と労働基準監督署への届出が必要になります。
労使間での協定締結が必要なのは、労働基準法第36条第1項で定められているためです。
また、労使間での協定締結の具体的な手順は以下のとおりです。
-
1. 労使間で交渉を行い、特別条項の内容に関して協議
2. 交渉がまとまり次第、書面で特別条項付き36協定を締結
労使間での協議の際、使用者は労働者側の意見を十分に聞き、健康に配慮した内容設計を意識しましょう。
また、原則的には会社側の代表者と労働者側の代表者が調印します。
なお、協定書に明記する必要事項は以下のとおりです。
-
• 限度時間を超えて労働させる具体的事由
• 業務の種類
• 労働者数
• 上限時間
• 健康確保措置
労使間での十分な協議と合意形成は、特別条項付き36協定の適正な運用のために欠かせません。
②就業規則の変更
特別条項付き36協定の申請で絶対的必要記載事項(労働時間、休日)就業規則の変更は必須であり、労働基準監督署に届け出る必要があります。
また、特別条項付き36協定は、労働基準法第89条の労働時間、休日、賃金に関する事項に影響するため、就業規則に記載しなければなりません。
なお、就業規則の変更手順は以下のとおりです。
-
• 特別条項の内容を就業規則に反映
(例:時間外労働の上限時間、健康確保措置の具体的内容を記載)
-
「就業規則(変更)届」を作成
-
• 効力発生日を合わせる
-
• 就業規則の変更と特別条項付き36協定の効力発生日を同一の日付にする
就業規則は、労働者の労働条件を定める重要な規則です。労働者に不利益な変更とならないよう、適切に特別条項付き36協定を反映させていきましょう。
③労働者への周知
特別条項付き36協定の申請方法の中で、労働者への周知は労働基準法で義務付けられており、定められた方法で全労働者に対して行わなければなりません。
労働基準法第106条第1項で、特別条項付き36協定や変更後の就業規則の内容を、労働者へ周知する義務があります。
また、労働基準法施行規則第52条の2で定められている周知方法は以下のとおりです。
-
• 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、または備え付ける
(例:事務所の掲示板に協定書を掲示する)
-
• 書面を労働者に交付する
-
(例:協定書のコピーを全従業員に配布する)
-
• 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録する
-
• 各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する
(例:社内イントラネットに協定内容をアップロードし、従業員がいつでも閲覧できるようにする)
労働者への周知は、特別条項付き36協定の適正な運用のために欠かせない手続きです。確実に周知が行われるよう、適切な方法の選択が求められます。
④労働基準監督署への届出
特別条項付き36協定の労働基準監督署への届出は、窓口提出、郵送、または電子申請の3つの方法があり、効力発生日の前日までに行わなければなりません。
労働基準法第36条第1項に基づき、特別条項付き36協定を締結した場合、労働基準監督署への届出が義務付けられています。
具体的な届出方法は以下のとおりです。
-
• 窓口提出:管轄の労働基準監督署に直接持参
• 郵送:管轄の労働基準監督署に郵送
• 電子申請:e-Gov電子申請システムを利用
届出は、特別条項付き36協定の効力発生のために必要不可欠な手続きです。届出期限を遵守し、適切な方法で確実に行うようにしましょう。
特別条項付き36協定に違反したらどうなる?

特別条項付き36協定に違反した場合、労働基準法第32条(労働時間)および第35条(休日)の規定違反で6ヵ月以下の懲役、または30万円以下の罰金が科せられます。
また、特別条項で定めた上限時間を超えて労働させた以下の事例があります。
電子機器メーカーが、月60時間を上限とする特別条項付き36協定を労働者と締結していました。
しかし、従業員6人に3ヵ月間、上限時間以上の労働を課し、最長で月106時間の時間外労働を行わせたケースがあります。
特別条項付き36協定に違反するのは重大な法令違反であり、厳しい罰則の対象です。適正な運用を徹底し、違反のないよう細心の注意を払うことが求められます。
参考:事例で理解!36協定違反と罰則とは?企業名公表や罰金をわかりやすく解説
36協定の特別条項で規制されている残業時間の上限を超えた場合はどう行動すべき?

36協定の特別条項で規制されている残業時間の上限を超えた場合、速やかに是正措置を講じ、再発防止策を実施しなければなりません。
なぜなら、特別条項付き36協定の違反は労働基準法違反で、罰則の対象だからです。
即時の是正措置には、残業時間が上限を超えた従業員の業務を他の従業員に振り分けたり、一時的に人員を増強し、業務負荷を分散させたりする方法が考えられます。
特別条項付き36協定で定めた上限時間を超えてしまった場合は、速やかに是正し、二度と同じ違反を繰り返さないよう、再発防止策の組み立てが重要です。
関連法令:労働基準法32,35条
法令遵守で特別条項付き36協定を申請しましょう
臨時的な事情がある場合に限り、36協定で定められた時間外労働の上限を超えての労働を可能にする取り決めが、36協定の特別条項です。
特別条項付き36協定の新様式(様式第9号の2)が制定され、より詳細な記載が求められるようになりました。法令を遵守した特別条項付き36協定を作成・申請が求められます。
本記事を参考に、労働基準法違反のリスクを避け、従業員の健康と安全を守るためにも、適切な運用を心がけましょう。
記事の冒頭でも申し上げましたが、36協定、労働基準法は国籍を問わず日本国内で働く労働者には原則適用されます。また、外食分野においては特別条項付36協定を締結する場合が通例となっていますが、特別条項付き36協定の適用条件や手続きが厳格化され、正しい理解と対応が求められています。
外国人人材の採用を検討、活用されている方も本記事を参考に適切な運用を行なってください。
弊社G-FACTORY株式会社では、飲食業界の人材不足を解消するため外国人人材の採用支援から就労者の在留資格・特定技能ビザ取得支援など企業側の受入支援まで外国人人材の採用サポートを一気通貫で行っています。
自社の飲食店で、外国人材による人材不足の解消を図りたい企業様は、以下のページからお気軽のご連絡ください。


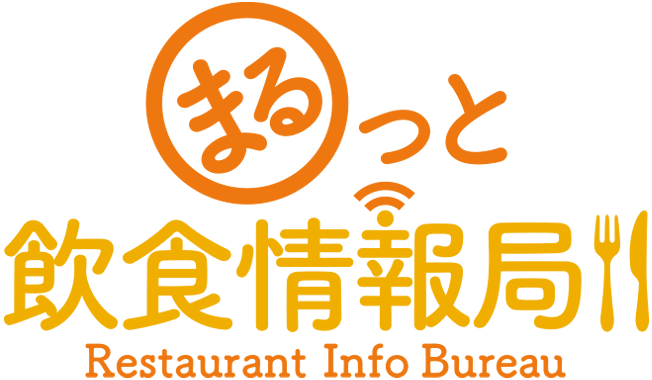

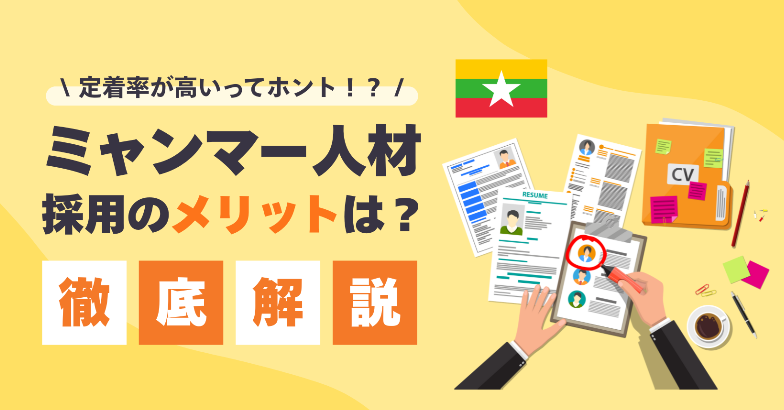

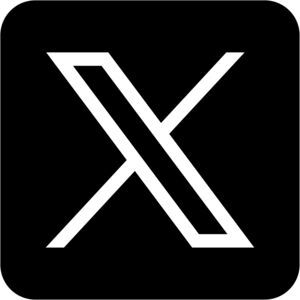



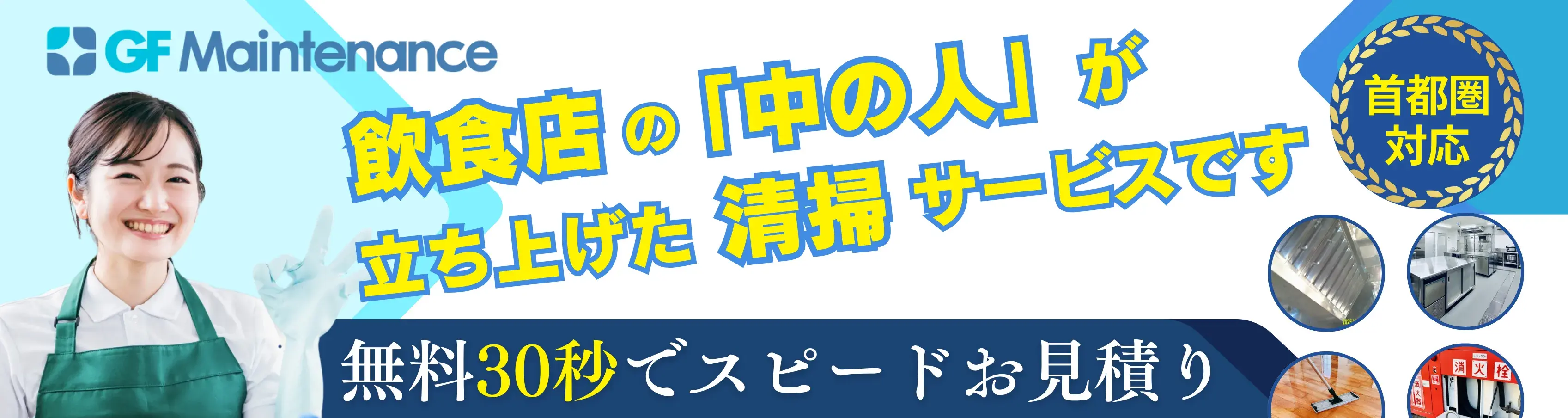
.png)
.png)
-1.png)
-1.png)
-1.png)

