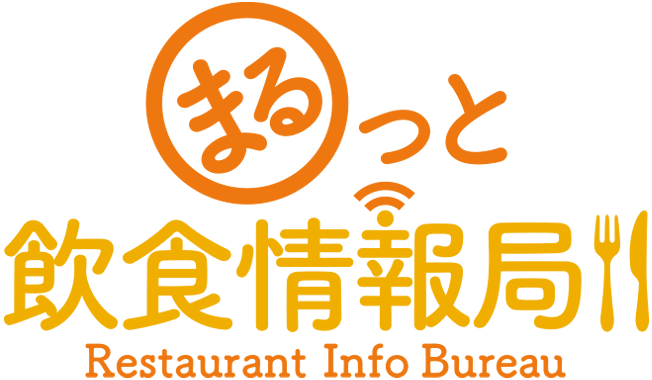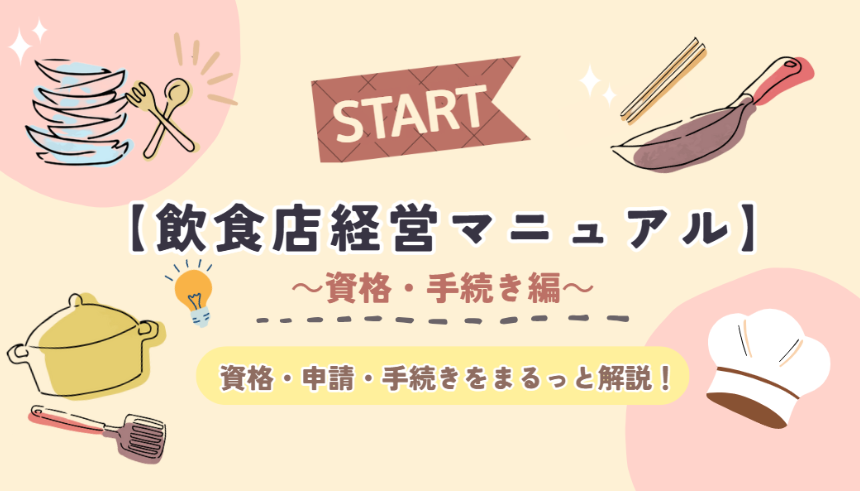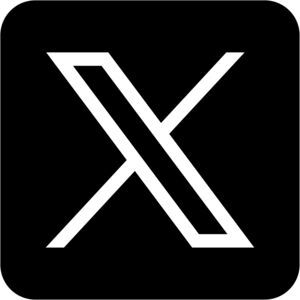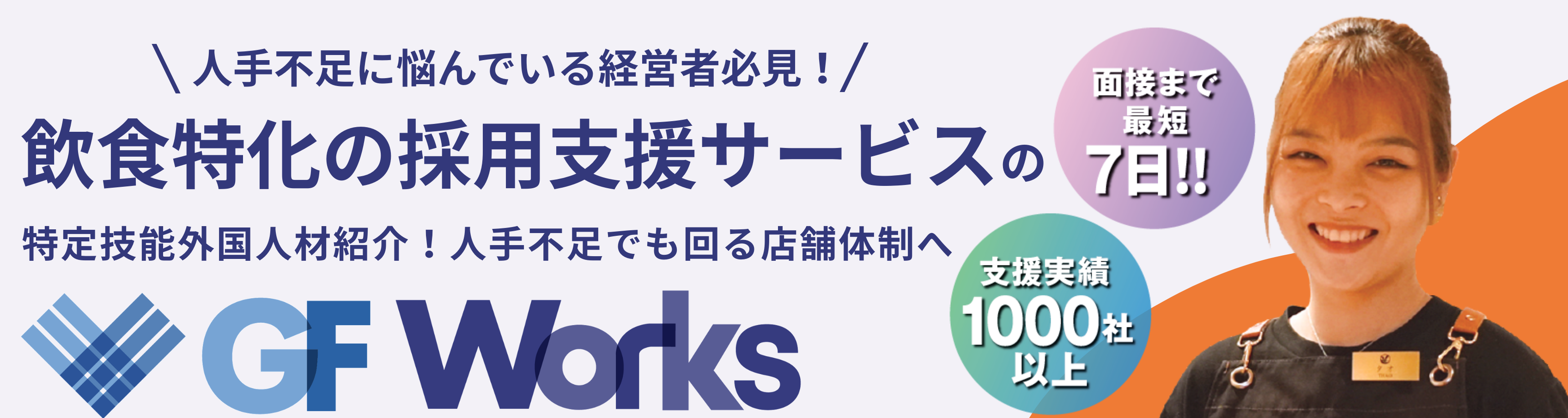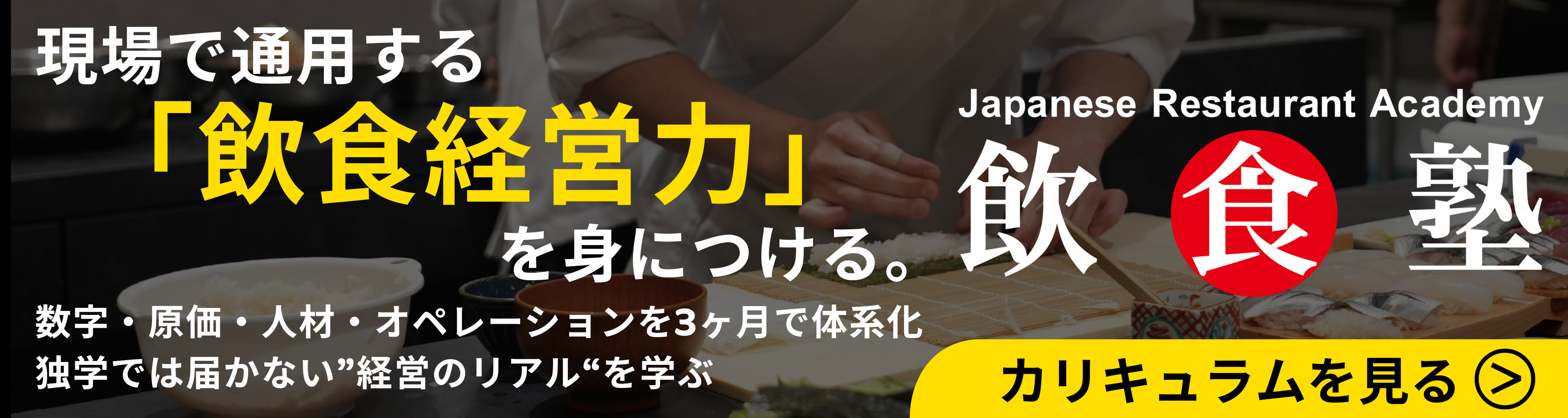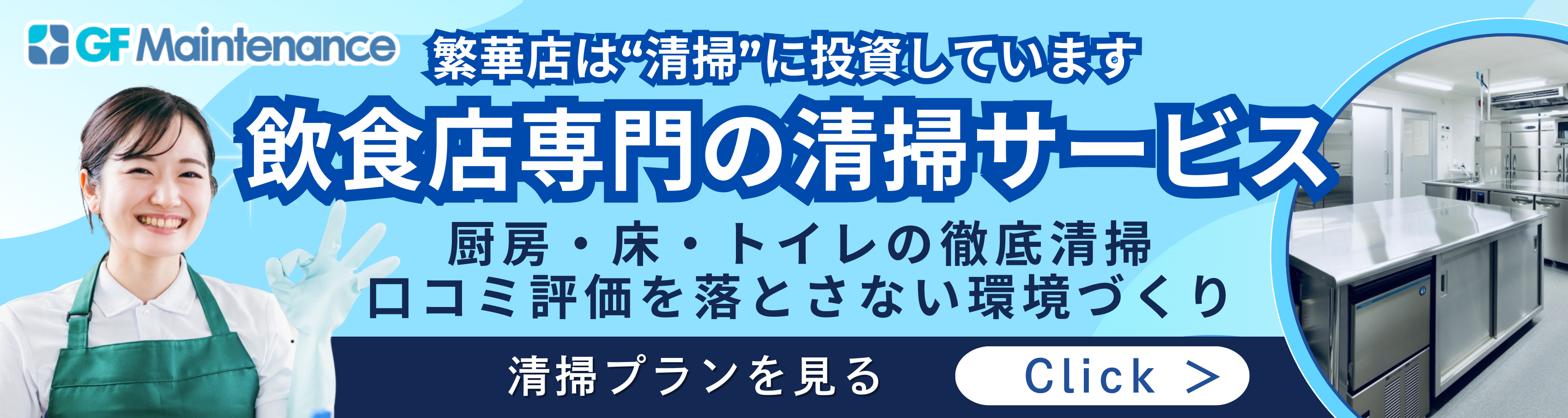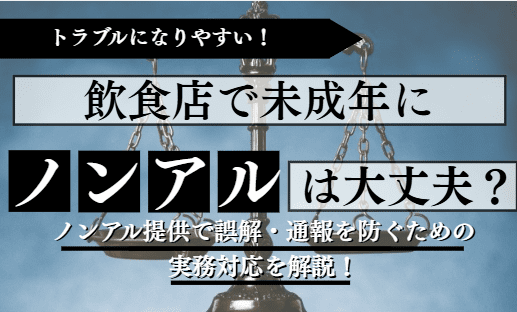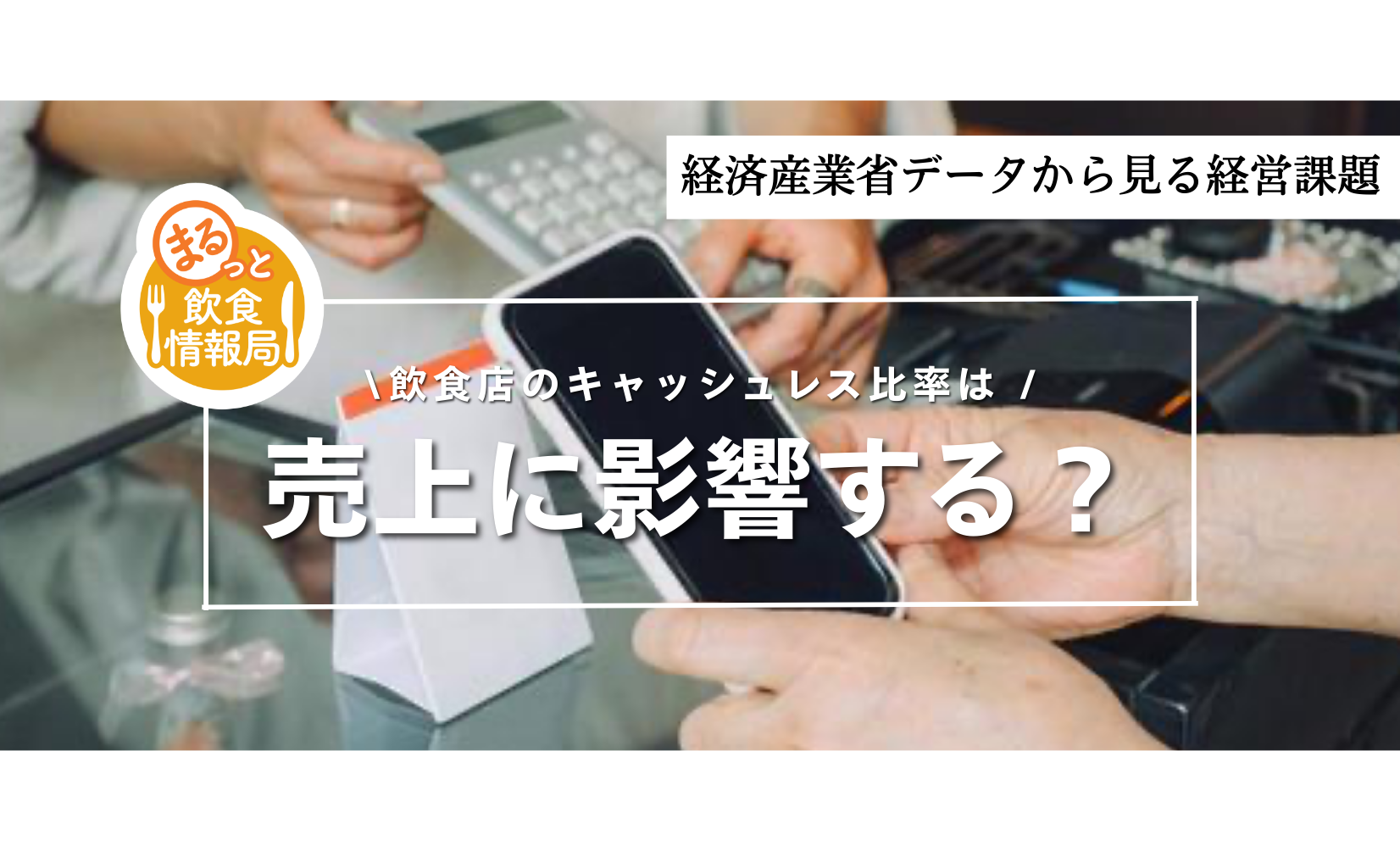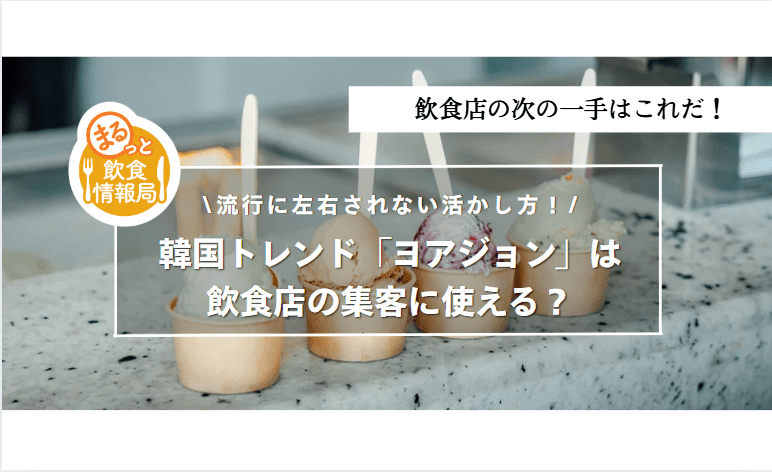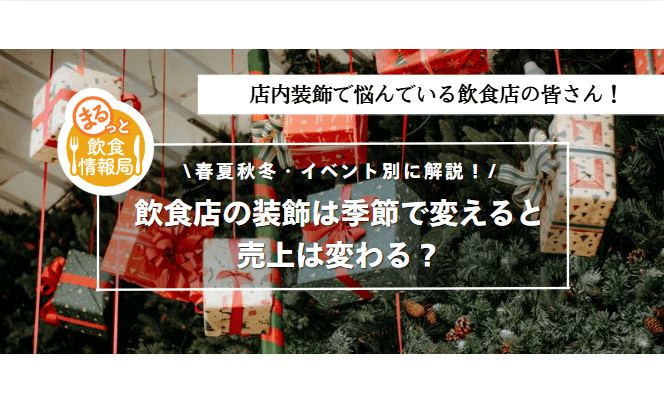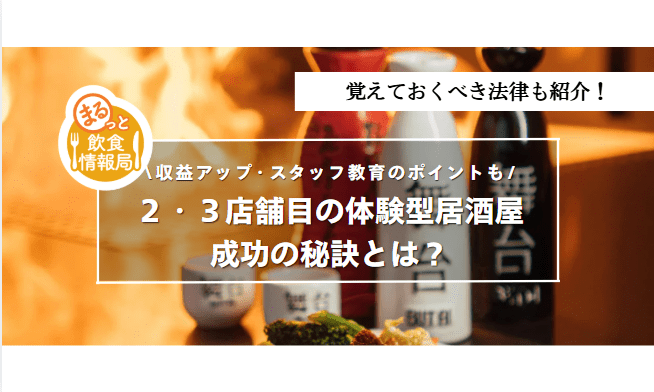2025/04/24
これで安心!飲食店の労働時間と休憩管理、店長向け簡単ガイド

従業員を雇用する際、以下のお悩みはありませんか?
「労働基準法で定められた労働時間の基準が分からない」
「残業時間の上限や長時間労働の規制を知りたい」
「労働時間と休憩時間、待機時間の違いが理解できていない」
本記事では、労働基準法で定められた労働時間の基本ルールから、法規制や上限時間などを詳しく解説します。
労働時間の正しい理解は、労働基準法違反のリスクを避け、適切な労働条件を整備するために不可欠です。
また労働基準法は国籍を問わず日本国内で従事する労働者には原則適用されることになります。
本記事を通して、労働時間管理のポイントを押さえ、働きやすい職場環境づくりにお役立てください。
弊社G-FACTORY株式会社では、飲食業界の人材不足を解消するため外国人人材の採用支援から就労者の在留資格・特定技能ビザ取得支援、企業側の受入支援まで外国人人材の採用サポートを一気通貫で行っています。
自社の飲食店で、外国人材による人材不足の解消を図りたい企業様は、以下のページからお気軽にご連絡ください。
シフト管理で守るべき労働時間とは?労働基準法の基本を解説
労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下にある時間を指します。使用者は労働者の労働時間に対して賃金を支払わなければなりません。
労働基準法では、原則1日8時間、1週間40時間を法定労働時間と定めています。
また、労働時間の該当可否は、就業規則や契約書ではなく、実際の指揮命令の有無で判断されます。
外国人労働者にも労働基準法は適用されますが、在留資格で労働時間に制限がかかる点に注意しましょう。
詳しくは、厚生労働省の以下のページをご参照ください。
飲食店経営に必要な労働時間の基本知識とは?
労働時間には、以下の4つの基本情報があります。
-
• 所定労働時間
-
• 法定労働時間
-
• 実労働時間
-
• 拘束時間
それぞれ詳しく解説します。
また、詳細は厚生労働省の下記ページにも記載されているので、下記ページも参考にしてみてください。
所定労働時間
所定労働時間は、就業規則や雇用契約書で定められた勤務時間から休憩時間を引いた労働時間を指します。
例えば、「始業が9時、終業が18時、休憩が1時間」の場合、所定労働時間は8時間です。
上記は企業で異なりますが、法定労働時間を超えない範囲で設定されています。所定労働時間を超えても、法定労働時間(1日8時間、週40時間)内であれば、時間外労働ではなく、割増賃金の支払い義務も生じません。
所定労働時間は、労働者の勤務時間を管理する上で重要な基準なので、意識しておきましょう。
法定労働時間
労働基準法で、1日8時間、週40時間が上限と定められているのが法定労働時間です。企業が法定労働時間を超えて労働させる場合は、「36協定」を締結しなければなりません。
また、法定労働時間を超える労働には、割増賃金の支払いが義務付けられています。しかし、特例的に36協定の特別条項のもとで、限度時間を超える残業が認められる場合もあります。
法定労働時間は、労働者の健康と福祉を守るための重要な規制であり、遵守しなければなりません。
実労働時間
実労働時間とは、実際に労働者が指揮命令下で働いた時間です。
休憩時間は含みませんが、始業前の準備時間や業務命令による勉強会・研修会も実労働時間に含まれる場合があります。
また、時間外労働が発生する場合、残業手当の支払い義務が発生するため、実労働時間の管理は、適切な賃金支払いと労働時間管理のためには欠かせません。
拘束時間
拘束時間とは、実労働時間と休憩時間を合わせた合計時間を指します。例えば、「9時始業、18時終業、1時間休憩」の場合、拘束時間は9時間です。
ただし、勤務中の待機時間は拘束時間に含まれますが、労働時間とはみなされないケースが多いため注意してください。
また、長時間の拘束は、労働者の健康や生活に影響を与える可能性があるため、適切な管理が求められます。

労働基準法で定められている労働時間の法規制とは?飲食店がシフト管理で注意すべき点
労働基準法では、労働時間に関する以下のような法規制が定められています。
-
• 所定労働時間の規制
-
• 残業時間の上限規制
-
• 長時間労働に関する安全配慮義務
-
• 労働時間の客観的把握義務
それぞれの法規制を詳しく解説します。
所定労働時間の規制
労働基準法第32条では、所定労働時間は原則1日8時間、1週間40時間までに制限されています。
ただし、商業・保健衛生業など一部業種では、常時10人未満の事業場は1週間44時間まで延長が可能です。また、管理監督者や変形労働時間制を採用した場合にも例外規定が適用されます(労働基準法第32条、第32条の2〜4)。
休憩時間は、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上を与えなければなりません(労働基準法第34条)。
休日は毎週少なくとも1日の休日、または4週間を通じて4日以上の休日を確保する必要があります(労働基準法第35条)。
上記の規制は、労働者の健康と福祉を守るために設けられたものであり、使用者は労働時間の適切な管理を行い、法令を遵守しなければなりません。
違反した場合には、是正勧告や罰則の可能性があるため、注意が必要です。
参考:労働基準法
残業時間の上限規制
働き方改革関連法の施行で、残業時間の上限が以下のように明確に定められています。
-
• 年間:720時間まで
-
• 月:100時間未満(休日労働を含む)
-
• 複数月平均:月80時間以内(休日労働を含む)
残業を行うには、労働基準法第36条に基づく「36協定」の締結が必要であり、協定締結後は労働基準監督署への届出が義務付けられています。
36協定で定める上限時間を超えての残業は、たとえ労働者の同意があっても違法なので注意してください。
長時間労働に関する安全配慮義務
月80時間を超える時間外労働が発生した場合、労働安全衛生規則第52条の2に基づき、該当従業員へ通知する義務があります。
疲労の蓄積が認められるケースでは、労働安全衛生法第66条の8に基づき、医師の面接指導を行う義務が発生します。
また、医師の意見を参考に、必要に応じて労働時間の短縮など適切な措置を行う義務も怠ってはいけません(労働安全衛生法第66条の8)。
長時間労働が継続すると、労働者の健康が損なわれるリスクが高まります。
労働時間の適切な管理とあわせて、職場環境の改善や労働者のメンタルヘルスケアにも注力するようにしてください。
参考:「産業医・産業保健機能」と「長時間労働者に対する面接指導等」が強化されます
労働時間の客観的把握義務
働き方改革関連法の改正で、企業は従業員の労働時間を客観的方法で把握する義務があります。
タイムカード、パソコンの使用記録、センサーなどの客観的な手段を使用しなければなりません(労働安全衛生法第66条の8の3)。
また、労働時間の記録は3年間の保管が義務付けられています(労働安全衛生規則第52条の7の3)。
自己申告制を利用する場合でも、従業員への正確な申告をうながし、不適切な運用が行われないような管理が求められます。

飲食店でも例外はある?法定労働時間の特例ケースとは
以下のようなケースでは、法定労働時間の例外規定が適用されます。
-
• 時間外労働協定(36協定)
-
• 変形労働時間制
-
• フレックスタイム制
-
• みなし労働時間制
それぞれの例外ケースを詳しく解説します。
時間外労働協定(36協定)
36協定は、労働者の過半数代表者または労働組合と使用者の間で締結される労使協定です。36協定に基づき、法定労働時間を超える時間外労働や休日労働が許可されます。
また、時間外労働には上限時間が設定されており、超過する場合には特別条項の設定が必要です。
なお、協定は行政官庁に届け出る義務があり、正式に承認されなければ無効なので注意してください。
変形労働時間制
変形労働時間制は、労使協定や就業規則に基づき、特定の期間内で平均的に週40時間を満たす働き方を調整できる制度です。
1週間単位、1ヵ月単位、1年単位の変形労働時間制があり、選択肢がさまざまあります。
忙しい日や週に労働時間を集中させ、閑散期には労働時間を短縮する運用が可能です。導入にあたっては、労働者への十分な説明を行い、同意してもらうようにしてください。
フレックスタイム制
フレックスタイム制は、一定期間内の総労働時間の範囲内で始業・終業時刻を労働者が自主的に設定できる制度です。
労働時間の管理が難しい業務に適しており、柔軟な働き方ができます。また、フレックスタイム制は、1ヵ月を超えない一定期間を対象とし、平均週40時間を超えない範囲で運用されます。
なお、就業規則への明記が義務付けられているので、労働者と使用者間の明確な合意が必要な点に注意してください。
みなし労働時間制
みなし労働時間制は、労働時間の算定が困難な場合に、あらかじめ定められた時間を労働したものとみなす制度です。
みなし労働時間制には以下の3種類が存在します。
-
• 事業場外みなし労働時間制
-
• 専門業務型裁量労働制
-
• 企画業務型裁量労働制
専門業務型裁量労働制は、厚生労働省が定める19業務(例:システムコンサルタント、デザイナー、研究開発など)に該当する場合にのみ適用されます。
また、企画業務型では、業務の遂行手段や時間配分に関して具体的な指示がない場合に活用されるので、理解しておいてください。

飲食店の労働時間上限はどこまで?労働基準法で定められた基準を解説
労働基準法では、以下のように労働時間の上限が定められています。
-
• 月間の労働時間
-
• 年間の労働時間
それぞれの上限を解説します。
月間の労働時間
1週間の法定労働時間40時間を基準に、月の最大所定労働時間は160時間と計算できます。時間外労働や休日労働を加えても、月100時間未満が上限です。
また、労働者の健康を守るため、時間外労働や休日労働を含めた月平均が80時間を超えない調整が必要です。
なお、36協定が締結されていない場合、法定労働時間を超えた労働は認められていないので注意してください。
年間の労働時間
所定労働時間が1日8時間、週5日勤務の場合、年間2096時間の法定労働時間です。
年間の法定労働時間は2096時間(週40時間×52.4週)で、時間外労働は最大720時間と定められています。ただし、休日労働や変形労働時間制の適用により、実際の労働時間には幅があります。
休日労働の時間も加わりますが、月平均80時間を超えないよう調整しなければなりません。法定上限を超える労働は労働者の健康を損なう恐れがあるため、厳しく規制されています。

労働時間はどう計算する?飲食店シフト管理に役立つ方法
労働時間は、就業が始まる時間から終わる時間までの休憩時間を省いた時間を指します。
具体的な労働時間の計算では、所定労働時間を基準に、超過分を法定内残業または法定外残業であつかいます。
法定労働時間は、1日8時間、週40時間までとされ、超える場合は割増賃金の対象です。また、割増賃金は通常の賃金の25%以上と定められています。
なお、計算例を以下で紹介しているので、参考にしてみてください。
計算例1:所定労働時間が1日8時間の場合、業務開始時刻が9時、労働終了時刻が18時、休憩1時間の場合、20時まで勤務した場合
-
• 総勤務時間:11時間(9時から20時)
-
• 休憩時間:1時間
-
• 労働時間:10時間
-
• 法定外残業:2時間(8時間を超過した分)
計算例2:所定労働時間が1日7時間の場合、業務開始時刻が9時、終了時刻が17時、休憩1時間の場合、20時まで勤務した場合
-
• 総勤務時間:11時間(9時から20時)
-
• 休憩時間:1時間
-
• 労働時間:10時間
-
• 法定内残業:1時間(17時から18時)
-
• 法定外残業:2時間(18時から20時)
労働時間と休憩・待機時間の違いとは?飲食店シフトで誤解しやすいポイント
労働時間と関連するその他の時間に関して、以下の表で比較しました。
|
労働時間 |
休憩時間 |
待機時間 |
仮眠時間 |
|
|
定義 |
労働者が使用者の指揮命 令下にある時間を指す |
労働者が労働から離れる権利を保障されている時間 |
使用者の指示や業務の必要性が発生するまで待機している時間 |
仮眠中でも業務対応が義務付けられている場合は労働時間に該当する |
|
判断基準 |
・使用者の指揮命令下で実務を行うかどうかが基準 |
・使用者の指揮命令下にないのが条件 |
いつでも業務に取りかかれる状態であるのが求められるため、休憩時間には該当しない |
・仮眠中でも業務対応が義務付けられている場合は労働時間に該当する |
|
事例 |
始業前の朝礼や業務準備など、指揮命令下にある場合も労働時間に該当する |
・判例では、指定された時間内で労働からの完全な離脱が可能な場合のみ休憩時間と認められる |
配送ドライバーの荷下ろし待機時間や早めに到着した場合の待機時間などが労働時間と認められた例がある |
当直中の産婦人科医や警備員の仮眠時間は、業務発生時に対応が求められるため労働時間とされる |
雇用の際は労働基準法の労働時間を遵守しよう!
労働時間は、労働者が使用者の指揮命令下にある時間を指し、原則1日8時間、週40時間が上限です。
ただし、36協定の締結や変形労働時間制、フレックスタイム制など、例外的な運用も認められています。
また、残業時間の上限規制や長時間労働の安全配慮義務など、労働者の健康を守るための法規制もあるため、しっかり確認するようにしましょう。
労働時間の計算では、所定労働時間を基準に、法定内残業や法定外残業を判断します。休憩時間や待機時間、仮眠時間との違いにも注意が必要です。なお、労働基準法違反は罰則対象のため、法令を遵守し、従業員の健康と働きやすい環境づくりに努めていきましょう。
弊社G-FACTORY株式会社では、飲食業界の人材不足を解消するため外国人人材の採用支援から就労者の在留資格・特定技能ビザ取得支援、企業側の受入支援まで外国人人材の採用サポートを一気通貫で行っています。
自社の飲食店で、外国人材による人材不足の解消を図りたい企業様は、以下のページからお気軽にご連絡ください。